毎度お馴染み、安価な中古ミラーレス機に様々なマニアックな
レンズを装着して楽しむというシリーズ記事。
第58回目は、まず、このシステムから。

カメラは、LUMIX DMC-GF1 最初期のμ4/3機であり、
現代では中古市場では値が付かない程になっている。
まあでも、使えないという訳ではなく、ピント合わせに
負担の少ないレンズと組み合わせて使用すれば良い。
レンズは、OLYMPUS M.Zuiko DIGITAL 45mm/f1.8
2011年発売のμ4/3専用AFレンズだ、他のマウントで使う事は
基本的にはできない。
μ4/3機装着時には90mm相当の画角となり、ポートレート用等の
目的を想定したレンズであろう。
オリンパスのHPでも「ママの為のファミリーポートレートレンズ」
と銘打っている。
価格が安いレンズであるが、写りは馬鹿にはできない。
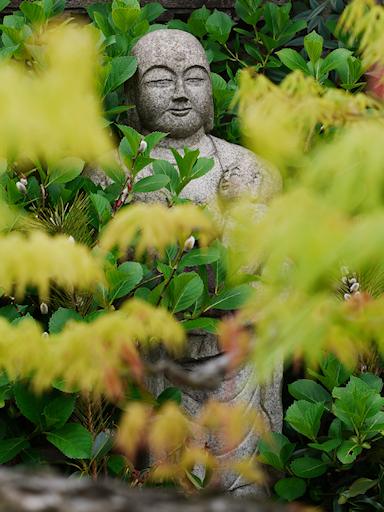
2010年代、こうした「エントリーレンズ」、つまり、デジタル一眼や
ミラーレス機のビギナーに、レンズ交換の楽しさを伝える為の
低価格レンズ群が各社から発売されており、それらはどれも描写力が
極めて優れている事に驚かされている。
まあ、一種の「お試し版レンズ」であるから、それも当然であろう。
もし、それらの性能がイマイチだったら、ビギナーはより高価な
交換レンズを二度と買おうと思わなくなるからだ。
ちなみに、エントリーレンズの価格だが、定価レベルでは
3万円台程度まで。実売価格は新品で2万円台程度、
中古価格は、1万円台のものが多いであろう。
ミラーレス機用の他、デジタル一眼レフ用の物が多数発売
されている。
本レンズの場合、エントリーレンズと言うわりには、高級感も
あって、かつ小型軽量であり、好ましい感じだ。
小型という点については、例えば本レンズのフィルター径は
37mmΦしかなく、市販のフィルターを装着するにも困って
しまう小型サイズだ。今回も(f1.8なので)ND4程度の減光
フィルターを装着しようと思ったが、勿論そんな小径フィルター
は持っておらず、おまけにあまり市販もされていない。
(ビデオカメラ用のフィルターとして少品種が販売されている)
念のため、37mm→46mmのステップアップリング(400円程だ)
のみ購入しておき、46mmΦのND4を装着するつもりであったが
今回は曇天であったので、f1.8のままでいけるだろうと判断。
しかし、本来はオリンパスのμ4/3機(E-PL2)に装着しようと
思っていたのが、E-PL2の最低ISO感度が200なので、ISO100
の使えるDMC-GF1を選択した次第だ、これだったら曇天でも
ぎりぎりで開放f1.8が使えるかも知れない。

あ~、しかし問題点が2点ほど発生。
まず1つは最短撮影距離近辺でAF精度が極めて悪くなる。
小さい被写体にAFが合わなかったり、背景にピントが行って
しまったりするのだ。ただし、これはカメラの設計が古い事も
理由かも知れない(後で試してみると、最近のμ4/3機では
さほど悪くも無い事がわかった)
ちなみに、最短撮影距離は50cmと、もう一声寄れて欲しい。
なお、AF精度はミラーレス機全般で、デジタル一眼レフに比べて
低く、AFだけに頼るのは苦しい、かといって「MF操作系」に優れる
ミラーレス機は多くなく、かつ、ミラーレス用純正AFレンズで
「MF操作性」に優れるものは皆無である。
そんな場合、アダプターで一眼用MF/AFレンズを使用時ならば、
高いMF性能を得られる機種もあるので、いっそそちらの方が
純正AFレンズよりも使いやすさを感じることが多い。
もう1つの問題点は、μ4/3機で純正AFレンズを使う際には
当然なのだが、撮影前に被写界深度およびボケ質の確認が
しずらい事だ。
ここのところ、ずっとアダプター使用でMFでばかり撮って
いたせいもあり、こういう当たり前な事が、いかに不便な
事かを改めて実感した。
勿論プレビュー操作を行えば良いのだが、アダプター操作系と
同じようにする為には、撮るたびにプレビューボタンを押し
かつ、戻す、という操作が入るのでやってられない。
よって、撮った後の自動再生画面を見ながら、絞りを変えて
何枚も撮影しなくてはならなくなる、これも勿論面倒だし、
GF1の低性能なモニターでは、被写界深度もボケ質も確認不能
なので、いずれにせよ、やってられない。
よって、今回はボケ質破綻とか、そういった細かいチェックは
無理だと判明、まあ、そういう目的にはEVF搭載の上級機利用が
良いであろう。が、AFレンズとGF1を組み合わせ、気軽に撮れる
のが、今回のシステム構築のコンセプトなのだ。
しかし、描写力的にはなかなかのものだ、特にシャープネスに
優れるように思う。ただ、元々はポートレート志向レンズで
あるから、あまりカリカリと解像力があって、結果的にボケ質も
固くなってしまうような性格は、コンセプト的に好ましくないで
あろう、なので、多少絞り込んだ時にシャープネスがぐっと向上
するような味付けにしているのだと思う(まあ、普通に設計すれば、
ほとんどのレンズはそういう性格になるが)

本レンズの中古購入価格は、2010年代で16000円程であった、
相場より若干安いが、ちょっと程度が悪い、と販売店側が
判断したからであろう。個人的には多少のキズやゴミは
気にしないので、安く買えた方が勿論ありがたい。
この値段、そして描写力からすればコスパは極めて良いと思う。
けど、じっくり使う事が出来ないというのも、ミラーレス機用
純正AFレンズの弱点である、上記の被写界深度やボケ質の事前
確認の問題、そしてMF使用時には、無限回転式ヘリコイドがアダと
なって、MFならではの速写技法(例:無限遠、最短等の、それぞれ
に指の感触だけで速やかに仮ピント合わせをする事等)が出来ない。
結局は、AFに完全に頼れるほど、ミラーレス機のコントラスト
検出方式は精度が良く無いと思っているし、大口径レンズでは
特に精度の他、測距点(というかピントをあわせる場所)の
選択においても、操作系上の問題が発生する。つまりAFが
どこにでも合うから、むしろ操作性的には面倒なのだ、よって
中央固定とせざるを得ないが、AFロックで構図変更すると
被写界深度の浅い大口径レンズではピントがずれてしまう
(コサイン誤差や、構えがそこまで厳密に安定しない事が理由)
まあ、本レンズの購入は微妙な選択だ、45mmはミラーレス機では
少々珍しい焦点距離かもしれないのだが、銀塩時代の標準レンズ
で十分代用可能だ、そちらであればむしろMF操作系でミラーレス機
のパフォーマンスを発揮させる事もできる。
でも、AF操作系で使うとして考えれば、良いレンズだと思う。
(ただし、AF操作系が優れたカメラである事が必須だ、
正直言って、そういうμ4/3機は、さほど多くない)
ライバルをあえて上げるとしたら、SIGMA A60/2.8DNあたりか?
両者ともに安価であるし、どちらも描写力が極めて高い。
(本レンズの中古相場は2万円弱、SIGMA60/2.8が14000円前後)
なお、PANASONICにもμ4/3機用の42.5mm/f1.7というレンズが
存在しているが、私は所有していない。その理由は価格が高い
からであって(中古相場25000円程度)、もし本レンズと同等の
描写力であるならば、コスパが良い方を私は選択する。
----
さて、次のシステム。

カメラは、FUJIFILM X-E1
AF/MFともに性能と操作系に多数の課題を抱えているカメラだ、
しかし長所も多く、使わないのは勿体無い。
ここのところ「限界性能チェック」で、難しいレンズばかり
あえて使ってきていた、だいぶ(かなり)辟易してきたので
今回は、気楽なトイレンズを使ってみよう。
レンズは、ニコンおもしろレンズ工房 ぎょぎょっと20だ。
本レンズは、すでに第18回記事で紹介しているが、その際は
マクロテレプラスと併用していて、なんだか良くわからない状況
であったので、再登場だ。
いわゆる対角線魚眼(風)レンズ、ただし、魚眼風に写る
のは銀塩・フルサイズ機での話であり、APS-C機であるX-E1に
装着時は、ちょっと歪んだ広角レンズとなる。
開放f値はf8 であり、X-E1装着時は30mm/f8相当の画角となる。

魚眼っぽくない写りだが、これはあえてそういう撮り方を
しているからでもある。
本シリーズ記事では、銀塩用の対角線魚眼をAPS-Cやμ4/3機
で使う場合、「魚眼によるデフォルメ効果は期待できない」
という理由から、逆に「デフォルメ効果を出さない」撮り方
を色々と模索している次第だ。
それをするためには、まず画面上の中心点を意識し、そこに
構図内の直線部分が、中心点に向かって集束するように構図を
意識して撮影すれば良い。つまり、その直線(対角線)は
魚眼レンズでは常に歪まないで写る。
(第12回記事で実例を挙げて詳しく説明している)
さて、本レンズの最短撮影距離は1mと、信じられないほど長い
また、ピント合わせ機構は無く、パンフォーカス前提のレンズ
である、加えて、当然絞り機構も持たない、これらの仕様は
本レンズが、ニコンでは唯一の「トイレンズ・セット」の
1本であるからだ。
「おもしろレンズ工房」の他の2本のレンズについては、
第13回記事で「ふわっとソフト兼ぐぐっとマクロ」を
第38回記事で「どどっと400」を紹介している。
興味があれば、それらも参照してもらいたいが、ただし、この
トイレンズキットは現代では入手困難であるので、念のため。

ピント合わせに致命的とも言える課題を抱えるX-E1であるから、
このようなトイレンズとの相性は当然極めて良い。
本「ぎょぎょっと20mm/f8」もそうだし、
第20回記事、第51回記事で紹介した、Xマウント純正の
FILTER LENS を使ってもそうだ。
つまり、X-E1のピント合わせの問題点が消滅し、逆に長所である
「ベルビアモードでの発色の良さ」「軽量であること」
「ローパスレス」「露出補正の操作性」などが浮かび上がってくる。
それだったら、X-E1は「トイレンズ母艦」とすれば良いかとも
一瞬思ったが、そうするには贅沢すぎる。すなわち、今度は
また別のルール(持論)である「レンズよりもカメラの価格を
あまり高くしない事」に、ひっかかってしまうのだ。
X-E1の中古購入価格は27000円程度であったので、
できれば3万円級以上のレンズの母艦にしたいところだ。
それに、もともと本機はXF56mm/f1.2R APD(第17回記事、
第30回記事)という特殊高性能レンズを使う為に購入したものだ、
それであれば十分に高価なレンズであり「カメラ2 対 レンズ8」
の予算配分を意識する持論にも合致する。
まあでも、APDは写り(特にボケ質)が凄すぎて、逆に何も
工夫しなくても良く写ってしまうので、飽きがきやすいレンズ
でもあったし、そもそもX-E1のAF精度が悪くて、あまり快適には
使用できない。
まあ、そんな状況であり、なんとか X-E1の弱点を消して実用的な
レンズを探している最中である。

本レンズの購入価格だが、3本セットで2万円ほどであったので
一応7000円程としておこう、現代では入手が難しく、あったと
してもレア品として「時価」になるので、無理をして探す必要は
無い。珍しいからと大枚叩いて買うと、極めてコスパが悪い
レンズとなってしまう。描写力はさほど悪くはなく、ちゃんと
写るレンズではあるが、一般撮影目的には使用できる条件が殆ど無く、
所詮はトイレンズ相当と思わなければならないであろう。
----
さて、次のシステム。

カメラは、望遠アダプター母艦の LUMIX DMC-G5
レンズは、TAMRON SP 60-300/f3.8-5.4 (Model 23A)だ。
こちらは、1980年代~2000年近くまで長期に渡って生産された
MFレンズである、マウントはアダプトール2なので、各社の
MF一眼レフに装着可能であった。
SPの名称は、高画質仕様を表しているが、残念ながら、さほど
高画質ではない。まあ、MF時代の望遠ズームは、まだ技術的に
発展途上であったので、当時としては、それなりに気合を入れて
開発したレンズであったのかも知れないが、そのあたりは流石に
30年以上も前の話なので・・

近接撮影は得意な方であろう、最短撮影距離は1.9mであるが、
300mmでこの距離で撮影すると、だいたい 2/3倍マクロに
なる模様だ。
μ4/3機であるDMC-G5に装着時の換算画角は、
120-600mm/f3.8-5.4となり、数値だけ見れば現代の最新
超望遠ズームのレベルと同等、しかもG5の便利なデジタルズーム
を併用すると、120-1200mm/f3.8-5.4という凄いスペックとなる。
また、デジタルテレコンを使ってさらに焦点距離を伸ばす事が
できるが、手ブレ補正の無いG5で、1500mm相当を超えると、
もうファインダーに被写体を入れる事すらままなら無くなるので、
1200mm程度迄で留めておくのが賢明だ。
なお、近接撮影時の撮影倍率もフルサイズ換算では1.3倍
又はデジタルズーム併用で2.5倍程度になるが、これもブレが
大きく実質的にそこまで倍率を上げる撮影は困難であろう。
ズームは前方直進式であり、この時代の他のMF望遠ズームと
比較すると、例えば、第47回記事のTOKINA 60-300/4.5-5.6
と同等であるが、第52回記事のFD70-210/4 や
第55回記事のTAMRON 80-210/3.8の逆直進式とは異なり、
また、第56回記事のOM75-150/4 の回転式とも異なる。
これらの中で直進式と逆直進式は、ズーミングとピント合わせ
が同時に出来るので極めて合理的だ。AFはまだ無い時代であった
ので、MFでの操作性を十分に意識して作られているのであろう。

何故沢山のMF望遠ズームを持っているかといえば、私は元々
ズームレンズはあまり好きではなく、単焦点派であった、
勿論、描写力が優れ、明るい、コスパが良い、などの様々な
メリットがあったからである。
だが、2010年代、ミラーレス時代に入ってから、ミラーレス機
の中古の相場下落が激しく、それを逆用して、安価で高性能な
中古機を購入する機会が激増した。特に高性能なDMC-G1は
自身で2台使っている他、友人知人用に、8~10台は買ったと
思われる。で、その時期、同時に「ジャンクレンズ大放出」
の時代が始まった。これは恐らく地方DPE店などが多く廃業した
事で、全国のMF時代の単焦点レンズやズームレンズが中古市場
に集められたのであろう、その中で程度の良いものは再整備して
それなりの価格で売られ、程度の悪いものは一々整備せず、
「ジャンク」として大量に中古市場で販売された。
その価格は、例えばMF標準(50mm)レンズが1000~3000円
という価格であり、私も何本購入したのかわからないくらい大量に
それらを購入した。まあ、その多くは、前述の友人知人用であった、
安価なミラーレス中古機にアダプターを使用して、MF標準レンズを
セットして2万円以下の低価格でシステムが組めたからである。

そして、友人知人の中には「せっかくの一眼なので、望遠でも
撮りたい」と言ってきた人も居た、まあ、ジャンクとして放出
されたものは、単焦点標準の他、標準ズーム、望遠ズームも
良く見かけたのであった。
だが、私は、銀塩MF時代、望遠ズームを殆ど使用していなかった
性能が悪く、コスパも悪いと思っていたからだ。
だから、どの望遠ズームが良いものか、経験から来るアドバイスが
全く出来なかった。
私は、自身で持っていない(使っていない)レンズを他人に
薦めることは絶対にしない、勿論、それは無責任だからだ。
なので、私も、そうしたジャンク望遠ズームを、7~8本買って
みた次第だ。しかし、ミラーレス機、例えばDMC-G1での使用は
ちょっと難易度が高い。手ブレ、ISO感度、ピント合わせ、
そしてそもそも被写体を探す・捉える(注:600mm相当とも
なると被写体にぴったりレンズを向けるのは難しい)など、
ビギナーの対応できるレベルでは無い、と判断し、それらの
望遠ズームは推奨する事なく、一部は「もし使えれば・・」と譲渡、
そして何本かのジャンク望遠ズームが手元に残ったので、それらを
本シリーズで順次紹介している次第だ。

本レンズの描写力は、やや物足りない、特に遠距離撮影に
おいて解像度が不足してしまう弱点がある。
SPという名称(高画質仕様)には、ちょっとそぐわない。
これだったら類似スペックのTOKINA 60-300/4.5-5.6
(第47回記事)の方が良いかとも思う。
そのレンズの購入価格は僅かに1000円だったし、おまけに、
最短1.5mと、本レンズよりも寄れる高性能レンズだ。
本レンズの中古購入価格は、2010年代に3000円であった、
勿論ジャンク扱いの相場である。
良く覚えていないが、アダプトール2が付属していたと思う、
その分で、TOKINA 60-300mmより高かったのかも知れない。
実は本レンズは2本買ってあった、もう1本はこれより少しだけ
高かったかも知れない、そのレンズは譲渡してしまったのだが、
まあ私も持っておいて方が良いかと思い、買いなおした次第だ、
いずれのレンズでも撮影しており、どちらも同様に描写力の
不足を感じていたので、レンズの個体差では無いと思う。
現代において必要なレンズでは無いが、一応参考まで。
----
さて、次は今回ラストのシステム。

カメラは、NEX-7
レンズは、ミノルタ MC ROKKOR 85mm/f1.7
1960年代後半のMF中望遠大口径レンズである、1970年にPF
(5群6枚を表す)の名称が追加された模様だが、レンズ構成等の
仕様は本レンズと変わらないようだ。
以前の第46回記事で、同時代のMINOLTA の傑作レンズ
MC PG 58mm/f1.2を紹介した際、絞りが故障して開放でしか
撮れなくなっていた、と書いた、実は、本レンズも同様の故障
を起こしている、いずれも齢50年に達するオールドレンズだ、
そろそろこの時代のレンズは耐用年数をオーバーしているのかも
知れない。
でも回避手段はある。以下の3つのアダプターを用いるのだ。

第52回記事で、TAMRON105mm/f2.5が同様な故障を
起こしていたのを回避した、そこで使ったEFマウント用絞り羽根
内蔵アダプター(写真の中央)を今回もまた用いている。
しかし、その記事では Fマウント→EFマウントであったので
問題は無かったが、今回は、MD→EFの変換を行わなければ
ならない。すると、フランジバックの関係で、通常のアダプター
では無理で、補正レンズの入ったアダプター(写真左)を用い
ざるを得ない。
「それだと画質が劣化するのでは?」
と思う人が居るかも知れないが、はい、それは正解である。
勿論補正レンズ入りアダプターは画質が劣化する、すなわち
解像度が低下し、絞り開放近くでは、ハロ(ハイライト部の
滲み)が出る、おまけに、焦点距離も伸びてしまうし、開放f値が
落ちてしまう事もある。
で、もし補正レンズなしのアダプターを用いると、今度は、
近接撮影専用となって、無限遠にピントが合わなくなる。
・・これは究極の選択だ、どちらを選んでも大きな弱点となり、
面白くない。
でも、今回は画質劣化の方を甘んじる事にした。
その理由だが、このレンズがとんでもないクセ玉だからだ。

ご覧のとおり、極めて変なボケ質である。
通称「ぐるぐるボケ」、50年以上前のオールドレンズで
たまにあったボケ質で、同心円状にボケが流れるという特徴
がある。
だが、コンパクト機のレンズとか、設計に無理をした超大口径
レンズとはでは、それはあったが、写真用レンズとしてちゃんと
販売された一眼レフ用交換レンズで、ぐるぐるボケを出すものは
さほど多くなかったと思う。
本レンズには、このクセがある事を承知していたので、今回は
補正レンズ入りアダプターでも問題ないと判断、つまり、最初から
酷いレンズなので、もうどこまで悪くなっても気にしないという事だ。
高性能レンズであれば画質劣化は困るが、低性能レンズでは、
多少悪くなっても大差ない。
それに、もしかすると「毒をもって毒を制す」で、より面白い描写に
なるかも知れない(?)

ボケ質はさておき、ピント面はわりとシャープなレンズだ、
だから、NEX-7のデジタルズームを用いて、数倍に拡大し、
300~400mm相当の望遠レンズとしても、まあまあ使える。
また、ボケが起きない平面被写体であれば、そもそもボケ質を
気にする必要も無い。その際、ピント面はシャープので、なんら
問題は無いであろう。
だが、極めて用途を選ぶレンズでもある、というか、このボケ質だと
立体的撮影にはまず使えない、平面撮影オンリーか?
そもそも本レンズを1990年代に購入した理由だが、MF時代の
ミノルタには85mmレンズが殆ど無く、これが一番の85mm大口径
レンズであったからだ、AF時代(1980年代後半)になってから、
ミノルタは名レンズ AF85/1.4を完成させるが、マウントもαに
なってしまい、MC/MDとは互換性が無い。
で、MFのミノルタシステムを組む上で、85mmを揃えようとすると
なかなか他に選択肢は無かった訳だ。
ちなみに、MD時代(1970年代後半~)になってから、MD85/1.7
と85/2が発売されているが、前者はMCと同じだ、と1990年代の
私は勝手に誤解した(実はレンズ設計が変わっている、さすがに、
本レンズの描写力の酷さは、メーカーも承知していたのであろう)
後者は、小口径であったので、当時は興味が持てなかったのだ。
しかし、購入後、このMC85/1.7の描写のあまりの酷さに愕然とした。
なにせ、その名レンズのα用AF85/1.4も、当時併用していたのだ
同じミノルタの85mmで、時代の差は20年あるとは言え、ここまで
性能差があるなんて、購入してみるまで予想もしていなかった。
その後、あまり使う事が無いレンズとなってしまい、2000年代に
デジタル時代に入ってからは、MC/MDレンズ用のアダプターが
作りづらい(補正レンズか、近接専用か)時代だったので、
余計に使わなくなった、それでも一応 MD→EFのアダプターだけ
は買っておいて、ごく稀に EOSに装着して使う事もあったが、
やはり使うたびに「酷いレンズだ」という事を再確認する
だけであった。
だが、今にして思う、こういうクセ玉こそ、ミラーレス時代に
おいては個性的で面白いのではなかろうか?と。

いつものボケ質破綻回避の技法を応用してみる。
今回、主に着目したのは、絞り値や撮影距離ではなく、背景の
絵柄だ。それがパターン化していたり、はっきりしていると、
グルグルボケと悪い相乗効果が出る、なので、背景が
パターン化されていない状況を選んでいる。
また、補正レンズアダプターのハロや球面収差も、いい感じに
ボケ部に乗ってきていて、絵画のようなトーンのボケとなった。
結局、レンズは使い方次第なんだろうなあ、と思う。
クセのあるレンズを、単純に弱点だと見なしてしまうか、
あるいは、なんとかそれを個性にするような方法を模索するか。
まあ、後者はなかなか難しい事だとは思うが、挑戦していくのも
面白いと思った次第だ。
----
本レンズの購入価格だが、1990年代に 16000円程であった、
値段は比較的安かったと思う、けど、この写りをどう思うか?
によって、本レンズの評価はずいぶんと変わってくるだろう、
一般的には、ダメダメレンズと言う事になるであろう、
こんなクセ玉を、なんとか使いこなそう、などと思う人の
パーセンテージは決して高くないと思う。
よほどのマニア向けレンズである、という結論にしておこうか・・
さて、今回はこのあたいまでで、次回シリーズ記事に続く。