年末恒例の【熱い季節】ドラボンボートの総集編記事。
![_c0032138_15240722.jpg]()
関西圏のドラゴンボート・ペーロン大会のうち、印象に
残った、優良な5大会を順次紹介していく。
なお、近年においては、ずっと異常気象が続いていて、
今年もいくつかの大会が台風等で中止となってしまった。
で、例年、本記事でベスト大会として選出されている、
静岡県・静岡市の「ツナカップ大会」も、昨年に続き
2年連続で今年も台風による中止という不運だ。
![_c0032138_15242223.jpg]()
ダントツのベスト大会となると思っていたが、やむを
得ない。自然の猛威には誰も勝てないという事であろう。
それよりも、各地で様々な被害が出ている事が心苦しい。
さて、本記事では、各大会の特徴をわかりやすくする為、
競技志向、大会環境、エンジョイ度、観戦の楽しさ、の
4項目を、★5つを満点として評価するが・・
毎年の状況で、それらの評価点は微妙に変化する、
ただまあ、評価点数が高い大会を順に選んでいる訳でも
無く、独自の視点での選出要素も多々ある。
結果として、昨年のベスト大会編と、あまり変わり映えの
しない状態となっているが、順次それらを紹介していこう。
----
では、まずは最初の大会。
![_c0032138_15243174.jpg]()
競技志向 :★★★★
大会環境 :★★★★
エンジョイ度:★★★☆
観戦の楽しさ:★★★★★
総合評価 :4.1
高島ペーロン実行委員会(滋賀県高島市役所等)主管の
大会。
「観戦の楽しさ」の評価点が5点満点の大会である。
毎回書いている事だが、本大会での独自艇の操船は
かなり難しく、「ターン有り戦」である事もあいまって
蛇行、スピン、沈没、接触、落水等のアクシデントが
多発する。
ドラゴンやペーロンは見た目よりも安全な競技であり
アクシデント率はレースあたり0.2%程度であるのだが、
本大会に関しては、それは約20%と、100倍の数値だ。
だが、これでもヨットやサーフィン系の競技よりも
まだ低い数値かも知れない、特にサーフィン系では
よほどの上級者でなければ、毎回の落水は必至だ。
![_c0032138_15243153.jpg]()
は1件のみ、しかもそれが、本大会に最も経験値を持つ
古豪チームであった為に、操船のスキルが課題なのでは
無くて、その「水域」(1レーンのターン直後の地点)
そのものの影響なのではないか?という話題が出た。
例えば、水流や水深等の影響で、特定の地点で操船が
難しくなるケースは、他大会でも条件によっては有り得る。
そして、本大会での強豪チームまでもが、準決勝戦で
同じ場所でスピンしてしまい、決勝進出を逃してしまうと、
その地点は「魔の水域」のように大会中は呼ばれていた。
ただまあ、毎年毎年同じ場所が危険水域となる訳でも無い、
この6年間、私が本大会を観戦していた感じでは、その
地点でアクシデントがあって、それが勝敗に影響した
ケースは、他には1件のみである。
それに、後で転覆したチームにヒヤリングしてみると、
その原因は、より速いターンを実施しようと、普段は
しない特別な措置をやったらしい。それが上手くいかず
コース取りと、漕手、舵手とのトータルバランスが乱れ、
体勢を崩して転覆してしまったそうだ。
まあ、その古豪チームが、「少しでも速く」と考えた
理由は推察できる。それは、その地元古豪チームは、
これまでの本大会での優勝・入賞回数が最多であって、
「地元最強」の称号を得ていたチームだからだ。
地元古豪チームが必死で頑張る程に、近年における本大会
はレベルが高い、それは数年前よりドラゴン専業チームが
多数本大会に参戦しているからである。
滋賀県の四天王(小寺、池の里、龍人、琵琶ドラ)や
地元若手強豪の「守のシルバニアファミリー」を初め、
他府県参戦ながらも本大会をホーム大会とする優勝経験
チームの「からしれんこん」、そして、「吹龍」や
「メタルスタイリスト」「ドリーマーズ」等と、多数の
ドラゴン専業チームによる競技志向の強い大会になりつつ
ある、この為、今年の本大会の評価では「競技志向」の
評価点を従前よりも加点している。
![_c0032138_15243260.jpg]()
専業チームが多数参戦している事により、地元系ビギナー
チームが手も足も出ない事である。これだと地元系チーム
は大会への参戦意欲を失ってしまうリスクもある。
本大会は数年前まで「実力別カテゴリー分け」であったが
何故か現在は1カテゴリーに1本化されてしまっている。
もしかすると運営側(自治体である)が、参戦チームの
実情に詳しく無いのかも知れない、すなわち「専業チーム
とは何か?」という点だ。
ここを理解すれば、従前のように「実力別カテゴリー分け」
に戻す方がベターであるという選択になるだろう。
まあでも、本大会は長い歴史を持ち、カテゴリー分けの
変遷も何度かあったので、少し遅れるかも知れないが、
その時代の状況に応じたカテゴリー分類に、また変化する
かも知れない。
----
では、次の優良大会。
![_c0032138_15244715.jpg]()
競技志向 :★★★★★
大会環境 :★★★★
エンジョイ度:★★☆
観戦の楽しさ:★★★★☆
総合評価 :4.0
JDBA(日本ドラゴンボート協会)、SDBA(滋賀県ドラゴン
ボート協会)主管。大阪府ドラゴンボート協会協力の大会。
例年、雨天になりやすい(その率は6割程)大会であるが
今年もまた、台風の影響で一時的な豪雨に見舞われた。
ただまあ、幸いにして中止や中断となる状況では無く、
雨天を吹き飛ばすほどの熱戦が行われた大会である。
![_c0032138_15244769.jpg]()
すなわち、現代の国内ドラゴン系大会で最も競技志向の
強い大会であり、遠く、熊本、沖縄、そして海外を含め
各地から超強豪チームが集結する。
ドラゴンはプロ競技とは異なり、「ランキング制度」は
無いのだが、もしそれを実施すれば、本大会は間違いなく
現在のドラゴンチームでのトップ(高)ランカーによる
頂上決戦と見なす事ができるであろう。
![_c0032138_15244783.jpg]()
本記事冒頭写真)よりも、本大会の方が競技志向が高い
のは、日本選手権は20人漕ぎである為、現代の世情に
おいては、20人もの主力漕手を集められるチームは
少ないからだ。
つまり、20人漕ぎはエントリー(参戦)自体の敷居が高い。
対して、10人漕ぎの本大会は、遠距離参戦等においても
チームの負担が若干少なく、主力漕手も集め易い。
それと、もし20人以上もの漕手を集められる大勢力の
強豪チームであれば、本大会では、10人毎に分割して
エントリーすれば良い訳だ。
本大会に(超)強豪チームが集まり、競技志向が高まる
理由は上記の通りである。
----
ところで、上記、高島ペーロンやスモール選手権での
「専業チーム」という扱いの話であるが、これらは
勿論「アマチュア」なのだが、一般的に想像するような
「プロ」と「アマ」の区分は、ドラゴン競技においては
適用されない。
以下、長い余談となる。
まあ、多くのアマチュア(スポーツ)競技の運営側は、
自治体や地元団体(商工会等)や地元企業等が主体と
なって行っているケースも多く、そこでは、参加選手
(チーム)は「全てアマチュアである」という認識で
あろう。
だが、いわゆるドラゴンで言う「専業チーム」に当たる
ような、日常的かつ専門的に、その競技の練習を行っていて、
もしその競技がプロ化すれば、すぐにでもプロチームとして
やっていけるような高いスキルを持つ、セミプロ層または
ハイアマチュア層が多数存在する状況自体には、地方大会等
の運営側の多くは気づいていない。
つまり、「世の中にはプロとアマチュアの2種類しか無い」
と思い込んでいる訳だ。
では、プロとアマの差は何か? ここが世間一般では
大きくカン違いをしている事だろう。世間の一般層では
プロとは「それを生業としてお金を稼ぐ人」と思っている
のかもしれないが、たとえば一部のドラゴンやペーロン
競技でも、勝てば賞金は出る、ただ、その賞金だけでは
生計が立てられないから、他に本業を持っているだけだ。
それは、プロ競技が存在する野球やゴルフその他でも
同様であり、アマチュアでも出場できるオープン大会に
出て、賞金を貰えばプロなのか? いや、そうでも無い
何故ならば、それだけでは食べていけないからだ。
であれば、「本業としているか否か?」がプロの定義か?
いや、それも不自然であり、例えば陸上競技の日本代表等で
企業に所属しながら、その競技を続けていたら、その競技
そのもので収入を得ている訳では無い、だからそれをプロと
呼ぶのは微妙だ。(注:「社会人」等と定義する場合もある)
すなわち、「お金を貰っているかどうか?」や「本業と
しているかどうか?」では、プロとアマの区別はつかない。
・・と言うか、世の中でのスポーツあるいは仕事において
そうした上記の定義での「プロ」と「アマ」のどちらにも
属さない人たちが沢山居る。いやむしろ、それが大多数で
あって、例えば、ゴルフの大会の賞金だけでやっていける
選手等は、ほんの一握りであり、他の仕事の収入で食って
いくしか無い訳である。あるいは音楽の世界でのバンドや
歌手でも同様の状態だ、たまにはステージに立つのだが、
それだけでは食べていけない人達が大半である。
また、それらの「腕前」や「スキル」も区別には無関係だ、
「歌が上手ければ即、それはプロである」とも言い切れない。
![_c0032138_15250694.jpg]()
スポンサー(企業や店舗等)が付いている、そこから
お金を貰えるならば、それはプロなのか? いや、そう
単純な話でも無いであろう。
あるいは、アマチュア劇団が、有料の入場料で、多数の
観客を集めて、お客を感動させる絶妙な演技を行ったとして、
だからそれはプロ劇団なのか? いや、何とも言えない。
![_c0032138_15250645.jpg]()
世間一般の視点(定義)では、プロとアマの区別は曖昧だ。
よって、世間一般で言うプロとアマの定義は成り立たない、
では、どのように区別するべきか?
私は、プロとは「その仕事やパフォーマンスを、観客や
ギャラリー等に対して「魅せる」事が出来、その結果
として「対価」を得ようとする/得る事が出来る人達」
と定義している。ここに、運動能力や技能や技術や才能
やセンスや、弁舌や歌の上手さ等は、あまり関係が無い。
つまり、その人が行う行為が「お客さんの方を向いている」
人達はプロであり、「(お金を払う)お客さんの方を
向いていない(=自己満足である)」人達はアマチュアだ。
極めてシンプルではあるが、これが真理である。だから
いくら演奏が非常に上手な音楽バンドであっても、あくまで
「オレのギターは上手くて格好いいんだ、オレの音を聴け!」
という感じのパフォーマンスでは、それが有料ステージで
あったとしても、プロとは言い難い。
つまり、世の中にはセミプロ級の人達が沢山居る訳だから、
そういう風に、その競技や芸術・芸能等に真剣に向き合う人達と、
そうでは無い人達との差異は、世の中が思う「プロとアマの差」
としての間違った定義よりも、それよりも、ずっと大きい。
つまり「好きこそものの上手なれ」を地で行く話であり
自分が好きで、その分野をずっと続けているならば、
下手に向上心等の無い、世間で言うところのプロよりも、
ずっと実力的には上回るケースが良くある訳だ。
あとは、その実力者・猛者達が「お客の方を向けるか否か」
そこが真のプロとして通用するかどうかの境目だ。
ドラゴン競技がプロ化できるか否かも、実はそこにかかって
いる。大会や競技体系全体を運営する為には、その費用を、
スポンサーや選手達自身から得るのではなく、その大半を
観客やファン層からの収益で得なければならない、そして
現代においてプロ競技として成り立っているものでは、
必ず、そのビジネスモデルが成立している。
![_c0032138_15250635.jpg]()
も、その競技が大流行していた時代(1970年前後)では
プロ化もされ、美人女子プロボウラーや、驚異の高得点を
叩き出す男性強豪ボウラーが人気で、TV中継もされていた。
しかし、後年にボウリングブームが去り、TV中継も無くなり
ボウリング場も減り、大衆の誰もがボウリングの事を忘れて
しまうようになっていくと、プロ競技の体系を維持する事が
難しくなる。
そこで、近年においては「P☆League」(Pリーグ)という
スタイルに転換し、またそこではプロ競技としての体系が
成立している。
「P☆League」とは、かつてのボウリングブームの際には
国民の誰もが知っていた(野球の「王貞治」氏よりも一般
知名度が高かった)美人女子プロボウラーの「中山律子」さん
(現:日本プロボウリング協会名誉会長)等により立ち上げ
られた「興業的」な主旨が非常に強いボウリング競技だ。
このPリーグは女子プロボウラーが主体となるリーグ戦で
優勝とかランキングとか、そういう点では一般的なプロ
スポーツ競技と同様だが、女子選手たちのコスチュームが
物凄い。まるで「コスプレか?」と思うような派手な衣装
に身を包み、かわいい(注:「プリティー」がPリーグの
Pの意味の一部となっている)女子選手達が、その外見に
まるでそぐわない剛速球や、強烈に曲がるカーブの球を
投げてストライクを連発する、という「ギャップ萌え」の
競技である。
ここでは勿論、その選手達の視点は100%観客を向いている。
何も、普通に競技をやるだけならば、派手なコスプレは
不用であろう、それは全て「観客を魅せる」為なのだ。
そう、本競技の立ち上げに尽力した「中山律子」プロは、
かつて、その競技自体の実力値(300点パーフェクトを
出している)も、さる事ながら、その美貌に注目されて、
TVの視聴者を釘付けにしたり、TV CMに出演したりで、
知名度を大幅にアップし、その結果として、世間での
ボウリングブームを大幅に加速し、各ボウリング場では
数時間待ちとなるほどのフィーバーを起こした。こうした
まさに時の人であったから、競技自体の実力値を高める事と
同等か、むしろそれ以上に「観客を魅せる事」の重要さを
よく認識しているのであろう。
大変余談が長くなったが、これは将来において、ドラゴン系
競技をプロ化したいと考える際に、非常に重要なポイントと
なる事だ。
つまり、プロ化するならば
「常に観客の方を見る事、魅せる事」
「観客に対し、「お金を払ってでも競技を見たい」という
パフォーマンスを実現できる事」
「観客に人気が高い、スター選手、スターチームを作る事」
あたりが、非常に大事である。
しかし、残念ながら現在のドラゴン系チームにおいて、
こうした視点で競技を行っているチームは皆無であろう。
逆に言えば、それ故にプロ化は難しい、とも言えるのかも
知れない。
観客の集客も課題だ、日本選手権や相生ペーロン等では
一般観客も多いが、すべてフリー(流れ)の観客であり
競技自体のファン層、というものは、殆ど存在していない。
チャンスがあるとすれば、この競技がメディアに注目
されるような、なんらかの出来事があった場合なのだが、
仮に世界大会等で優勝したりして、マスコミに取り上げ
られたとしても、チームや選手達が、アマチュア目線で
観客や大衆の方を向いていなければ、それは単なる
「一過性のニュース」で終わってしまう。
実際、ブレイクのきっかけがあった他のマイナー競技も
過去にいくつかあったのだが、残念ながら選手達や協会の
視点がアマチュア目線であったので、それらのマイナー競技
がプロ化される(つまり、ビジネスとして成り立たせる)
動きはあまり無かった。
現代においては、「スポンサー」は、単にお金を出して
くれる資産家や金満家等では無い。彼らは、その競技が
成長し、将来的に自身に利益をもたらしてくれると判断
する場合にのみお金を出す。すなわちそれは「投資」であり
決して「今、広告をするからお金を出してくれ」という
交渉が成り立つ訳では無いのだ。
(参考:昔の時代での芸術家に対する「パトロン」という
感覚であろう。パトロンは売れない絵描きなどの才能に
目を付け、生活を支援しつつ、後年に、有名になって
価値が上がった、その画家等の絵を高く販売する)
現代のネット社会では広告ビジネスモデル(アフィリエイト)
が全盛であるが、このビジネスモデルは未来永劫に成り立つ
訳では無い。仮に広告を出す場を動画サイト等の人気サイト
で作り上げたとしても、その広告による宣伝効果があって
実際に商品やサービスが売れて、広告主の収益が向上しない
限りは、無駄な広告や出費となってしまう訳だ。
(だから、近年のTV CM等では、効果が少ないから広告主が
減り、たいてい同じ企業ばかりがCMを流している。
流しすぎで、そればかりにお金を使っている悪印象もある
位なので、賢い消費者では「TV CMを行っている企業の商品
は購入しない」という選択をしているケースも多々ある)
よって、近未来の収益構造においては、ファウンディング
(投資型、資金調達型)のモデルが主になると予想できる、
これは、その競技、個人、事業、物品等において、
「今、お金を出しておけば、将来により大きい収益がある」
という観点である。(前述の「パトロン」も同じ)
事実、美術品とかカメラ等でもそうだが、投機型の商品は、
非常に高額で取引される。その理由は、その商品そのものに
それだけの高い価値があるからでは無いだろう、
「それを買えば、将来にさらに値上がりして高額に売れる」
(と考える)からである。
まあ、そういってしまうと身も蓋も無いが、要はその
商品、事業、個人、作品、競技等に将来性があるから、今、
その分野にお金を出して育て、将来での回収を狙う訳だ。
極めて余談が長くなったが、ここは現代社会を理解する
上で非常に重要な事だ。
![_c0032138_15253442.jpg]()
有力なスポンサー(広告主)を探せば良い訳では無い。
まず、選手達が「観客を魅せる」競技として意識改革を
行い、その上で、この競技が将来的にビジネスとして
通用する事を見越した投資家にプレゼンして資金調達を
行う必要がある。つまりここでも「お客目線」が必要で
あり、ここで「お客」(=金を出す人)のスポンサー自体も
儲かる、Win-Win関係を提案していかなければならない訳だ。
簡単な話では無いが、今のままドラゴン競技を続けて
いても、年々運営が苦しくなってくる可能性もあり、
それでは選手達の大会参加料は値上げしていくばかりである。
事実、2021年の「ワールドマスターズゲームス関西」
でのドラゴン競技の参加料は1人あたり15000円と高額だ。
別競技では、マラソン等の参加費は2~3万円となる場合も
あると聞く、これが、アマチュア競技を自己資金で
運営する場合の実情であり、これでは選手達も、そう
簡単には各大会にエントリーできなくなってしまう。
そうならないようにするには、競技自体をプロ化して、
「お金を払って参加する」のではなく、「お金を貰って
参戦する」に変えていく必要がある。しかしそうなった
としても、アマチュア目線で「お金が貰える、ラッキー」
と思うようではプロにはなれない。プロとして通用する
為には、「観客たちを魅せて、そこからお金を貰う」
という視線が必要なのだ。人気商売とも言える訳だから
自身が速い(良く漕げる)というだけでは通用しなくなる。
長い余談となったが、とても重要な事だ。
今すぐに、どうのこうの、という話では無いが、将来的に
ドラゴンやペーロンをプロ競技化したいのであれば、
こうした様々な事を考慮する必要があり、かつそれは
競技の運営側だけが考えるものではなく、競技に参戦する
選手側においても、様々な「プロ」としての意識改革が
必要になる、という点が重要だ。
----
さて、では、3つ目の優良大会。
![_c0032138_15253496.jpg]()
競技志向 :★★★
大会環境 :★★★★★
エンジョイ度:★★★★
観戦の楽しさ:★★★☆
総合評価 :3.8
主催、関西エアポート株式会社(KIXと伊丹を運営)
JDBA(日本ドラゴンボート協会)主管、和歌山ドラゴン
ボート協会協力の大会。
今年で16年目を迎えた長寿大会である。
長い余談を前述した「スポンサード」という点では、
非常に参考になるのが本大会であり、本大会には多数の
有名企業や大企業が、なんらかの形でスポンサーと
なっている事は、特筆すべき特徴である。
本大会においては、VIP専用とも言える「特設観覧席」が
存在している。そこで、大会運営側の関西エアポート社と
他のスポンサード企業と、どんな話が行われているのかは
知らない。でも、結果的に、その特設観覧席が設置された
以降では、有名企業等のスポンサーが増えているのだ。
2018年に最初にその特設観覧席が設置された際、一部の
選手達の間では、「あの観覧席、大会の後では壊して
しまうらしいよ、勿体無いね」という話が囁かれた。
だが、壊してしまったとしても、その投資効果は抜群だ、
その存在によりスポンサードが多数増えているならば、
むしろ、どんどんやるべきなのであろう。
私は、これを「秀吉の一夜城」方式と呼んでいる。
それは戦国時代、攻城が難しい敵方の堅固な城の目前に
短期間で仮の城を築城し、それにより敵方の戦意を
削いで、講和や攻城に持ち込む特殊な心理戦術である。
KIX大会での「一夜城」が、実際にどのような効果が
あって、どのような営業交渉が行われているのか、
までは良くわからない(知りようが無い)
勿論、関空側のスポンサード交渉の上手さもあるだろう。
ただまあ、非常に参考になる「プレゼンテーション」で
あるとも言える。現代における様々な営業・IRなど
に係わる商談や交渉では、こうした個性的かつ切り札的な
手法が有効であろう事が如実にわかる方法論だ。
前述しているドラゴン競技のプロ化の際には、重要な
参考事例として、学んでおくべき内容だと思う。
![_c0032138_15253478.jpg]()
の評価点が5点満点である。交通の便、駅近の会場、
多数のスポンサードにより近年では極めて整備された
大会観戦設備、そうした点がとても優秀である。
その結果として、大会の雰囲気も良い。幸いにして
競技志向もあまり高く無い為、スポンサー企業チーム
等でも、稀に決勝戦とかに進出して大いに盛り上がる。
結果として大会全体の「エンジョイ度」も好評価だ。
また、ビギナーチームの比率が高い事は、むしろ
競技志向よりもエンジョイ度を優先するという、本大会
の方向性やコンセプトに、とてもマッチしている。
専業チームの参戦数が減っているのは、本大会が、現在
では希少な20人漕ぎを主体とした大会であり、専業チーム
の現状では、20人の漕手を揃える事が難しいからだ、
しかし、現在ではそれがむしろ良い結果に繋がっていて、
関空関連、スポンサー企業関連、自治体関連等の多数の
ビギナーチームが、純粋に競技を楽しめる環境が構築
されている。
ビギナーチームの多くは若い選手達で構成されていて、
一流企業や自治体等での美人選手も多い状態だ。
男性層の生涯未婚率が増えてきていて、社会的にも問題
になりつつある(例:高齢化社会となる)現代の世情では、
仮に本大会を「婚活」の場とする事も、決して「不謹慎だ」
とは言い切れないようにも思える。
で、この大会で、専業チーム等が「必死のパッチ」で
漕いでいるのは、やや違和感もあるような様相になりつつ
ある状態であり、本大会では、ある程度は、スポンサード
となっているような運営関連のチーム達に楽しんでいただく
事も考えるべきであろう、そうしたスポンサード企業群が
無ければ、大会自体の開催も危ぶまれてしまうのだ。
![_c0032138_15253459.jpg]()
惜しむらくは、国内の選手達も、もっと積極的に
海外チームと交流を図るべきであろう、海外の人達と
しゃべり放題という、こんな素晴らしい機会は滅多に
無いのだから・・
----
では、4つ目の優良大会。
![_c0032138_15255769.jpg]()
競技志向 :★★★☆
大会環境 :★★★☆
エンジョイ度:★★★
観戦の楽しさ:★★★★
総合評価 :3.5
びわこペーロン実行委員会(びわこ放送、滋賀県ドラゴン
ボート協会等)主管の大会。
本大会は、少々アンバランスな課題がある大会だ。
およそ10年ほど前までは、本大会は地元のお祭り的な
様相の強い大会であり、いや、むしろ滋賀県に多数ある
大企業における「福利厚生」を主眼としていた大会で
あったとも言える。(つまり、社員レクレーションだ)
ところが、10年程前から、この大会を「競技」と見なす
ドラゴン専業チームが多数参戦を開始、すると当然ながら
全カテゴリーの上位チームは全てドラゴン専業チーム一色
となってしまい、全く手も足も出なくなった地元企業系
ビギナーチームからは「プロ(と彼らは思っている)の
チームがこの大会に参加するのは不公平(場違い)だ」
という不満が多く出るようになってしまった。
すぐさまカテゴリー分けを見直し、専業チーム群を
競技専用カテゴリーに封じ込めてしまえば良かったのだが
例によって、そういう抜本的措置は担当者が頻繁に変わる
地方大会では難しい、基本は、前年までのやり方を踏襲
せざるを得ないからだ。
数年前までは「このままでは大会の主旨が崩壊する」と
私は懸念を強く持っていたのだが、まあ、とは言え、
ドラゴン専業チームには責任は無い、あくまで彼らも
お金を払って大会に参戦する「お客様」なのだ。
まさか「ちょっと地元に気遣って、手を抜いてください」
などとは言う訳にはいかないだろう。
「遅いのは練習不足だからだ、我々はちゃんと練習して
いる、だから速いのだ」という論理で一蹴されてしまう。
![_c0032138_15260609.jpg]()
企業チームの一部が、そうしたドラゴン専業チームに
触発されて、かなり本格的な練習を重ねるようになって
きているのだ。
つまり彼らは、「専業チーム」の何たるかを理解し、
「それに勝つには、自分たちも多数の練習を重ねるしかない」
という事に気づいたわけだ。
一部の企業チームは、専業チームに倣ってカーボンパドルを
装備、そのチーム数は年々増えていて、今や、地元強豪企業
チームの殆どはカーボンで武装している。
また、専業チームがプロチームでは無い事を理解した
企業チームの一部は、OPAL等の練習場で、専業チームからの
厚意での直接指導を受け、その実力値を高めている。
今年2019年では、最も地元チームの入賞が困難な競技志向
の極めて高い「20人漕ぎ一般」の部で、ついに地元チーム
「シンコーメタリコン」(企業系)が3位に初入賞。
これまで約10年間は、全て入賞は専業チームだった訳だ。
こういう動向となるのであれば、あえて「チャンピオン
リーグ」等の「専業チーム専用カテゴリー」を設置する
必要は無いかも知れない、専業チームは、うまく地元チーム
に良い影響を与え、ドラゴン競技の育成に寄与している
からである。
まあただし、全ての地元チームがそうである訳でも無い、
依然、本大会は企業の福利厚生での「夏のレジャー」であり、
競技とかでは無く、純粋に大会を楽しみたいと思う参加
選手達が大半(およそ7~8割)なのだ。
その微妙なバランス感覚を意識した上で、ドラゴン専業
チームは、本大会に参戦し、競技自体の育成に少しでも
配慮していただければ幸いだと思う。
----
では、ラストの優良大会。
![_c0032138_15260620.jpg]()
コンテスト(大阪府・高石市・大阪府立漕艇センター)
競技志向 :★★☆
大会環境 :★★★☆
エンジョイ度:★★★☆
観戦の楽しさ:★★★☆
総合評価 :3.3
地方協会による小規模大会である。
以前は、「大阪府民体育大会」という名称であり、
これは大阪府全体の体育協会に加盟する各競技団体が
少なくとも年に1度は、その競技を実施する事が
必要とされている。
で、2020年の東京オリンピック開催を機会に各地の
様々な団体・行事での「体育」という名称が「スポーツ」
に改められていく状況がある模様である。
いち早く、本大会も「大阪府民スポーツ大会」となり、
来年2020年は、従前の「体育の日」は「スポーツの日」
と名称変更し、オリンピック開会式の日(7月24日)
に変更され、前日の「海の日」と合わせ4連休となる。
(注:2021年からは「スポーツの日」は従前の
「体育の日」と同じ、10月第二週月曜日に戻る)
さて、本大会を取り上げたのは、別に「スポーツ」に
名称変更されたからでは無い。
本大会では史上初の「舵取りコンテスト」が行われた。
この歴史的価値を鑑みての、ベスト大会選出である。
そういう意味では、今年静岡県御前崎市で実施された
「ドラゴンボート・パワーバトル」(一種の綱引き競技)
も、歴史的価値が高い大会であったと思う。
ただ、開催日(会場)の都合で、その大会は、前述の
びわこペーロンと同日開催となってしまい、私も御前崎へ
観戦に行けなかったし、逆に静岡県のチームも、琵琶湖
に来る事ができなくなってしまっていたので紹介困難だ。
別の日に開催できるならば、それを希望する次第である。
ちなみに、鳥取の「東郷湖大会」も例年、びわこペーロン
と同日開催になっていて、そちらも一度も観戦に行けて
いない次第だ。重複日大会開催は、私ならずとも、参戦
チームにも迷いが生じるだろうし、いろいろと会場の
都合はあるだろうが、できれば重複しない方が望ましい。
![_c0032138_15261440.jpg]()
チーム毎のタイムを重要視するのではなく、舵手の
技能を競うスラローム型のタイムレースである。
漕手・鼓手については、舵手による自由裁量だ、
それらの人数を舵手が自由に決める事が出来るという
特異なレギュレーションである。
漕手を増やせば、速くはなるが、舵による操船が難しい。
その逆は、軽くなり操船が容易だが、遅くなる。
鼓手を外せば軽くはなるが、漕手のペース管理が困難だ、
これらを上手くバランスさせる手法は、まだ今回の
大会が第1回目なので、セオリーが組み上がっていない、
今後、経験的に「鉄板」の方法論が出来てくるであろう。
で、何故こうした試みが行われるか?、については、
これは各地のチームや協会でも課題となっている
「慢性的な舵手不足」である。
そもそも、ドラゴン(ペーロン)選手の多くは、
「漕ぎたい」から競技を行っている訳であり、舵手の
なり手(希望者)は、とても少ない。
それに加えて、舵手には高い技量が必要とされる、
また、責任の重いポジション(例:舵手が艇を曲げて
しまえば、即、そのチームは敗退だ)でもあるから、
そう簡単に漕手から舵手への転向も困難である。
よって、「舵手の育成」を主眼としたのが、本大会の
舵取りコンテストである。
その効果は早速少し出てきていて、コンテストへの
挑戦者は、普段からの舵手では無く、チームの漕手で
あるケースも何人か出てきている。
![_c0032138_15261479.jpg]()
大会において、是非、同様な試みを行う事を推奨したい、
どの地区やチームにおいても「舵手の不足」は深刻な
問題であろうからだ。
----
さて、本記事はこのあたりまでで、次回も総集編として
「ベストチーム編」を書く事にする。

関西圏のドラゴンボート・ペーロン大会のうち、印象に
残った、優良な5大会を順次紹介していく。
なお、近年においては、ずっと異常気象が続いていて、
今年もいくつかの大会が台風等で中止となってしまった。
で、例年、本記事でベスト大会として選出されている、
静岡県・静岡市の「ツナカップ大会」も、昨年に続き
2年連続で今年も台風による中止という不運だ。

ダントツのベスト大会となると思っていたが、やむを
得ない。自然の猛威には誰も勝てないという事であろう。
それよりも、各地で様々な被害が出ている事が心苦しい。
さて、本記事では、各大会の特徴をわかりやすくする為、
競技志向、大会環境、エンジョイ度、観戦の楽しさ、の
4項目を、★5つを満点として評価するが・・
毎年の状況で、それらの評価点は微妙に変化する、
ただまあ、評価点数が高い大会を順に選んでいる訳でも
無く、独自の視点での選出要素も多々ある。
結果として、昨年のベスト大会編と、あまり変わり映えの
しない状態となっているが、順次それらを紹介していこう。
----
では、まずは最初の大会。

競技志向 :★★★★
大会環境 :★★★★
エンジョイ度:★★★☆
観戦の楽しさ:★★★★★
総合評価 :4.1
高島ペーロン実行委員会(滋賀県高島市役所等)主管の
大会。
「観戦の楽しさ」の評価点が5点満点の大会である。
毎回書いている事だが、本大会での独自艇の操船は
かなり難しく、「ターン有り戦」である事もあいまって
蛇行、スピン、沈没、接触、落水等のアクシデントが
多発する。
ドラゴンやペーロンは見た目よりも安全な競技であり
アクシデント率はレースあたり0.2%程度であるのだが、
本大会に関しては、それは約20%と、100倍の数値だ。
だが、これでもヨットやサーフィン系の競技よりも
まだ低い数値かも知れない、特にサーフィン系では
よほどの上級者でなければ、毎回の落水は必至だ。

は1件のみ、しかもそれが、本大会に最も経験値を持つ
古豪チームであった為に、操船のスキルが課題なのでは
無くて、その「水域」(1レーンのターン直後の地点)
そのものの影響なのではないか?という話題が出た。
例えば、水流や水深等の影響で、特定の地点で操船が
難しくなるケースは、他大会でも条件によっては有り得る。
そして、本大会での強豪チームまでもが、準決勝戦で
同じ場所でスピンしてしまい、決勝進出を逃してしまうと、
その地点は「魔の水域」のように大会中は呼ばれていた。
ただまあ、毎年毎年同じ場所が危険水域となる訳でも無い、
この6年間、私が本大会を観戦していた感じでは、その
地点でアクシデントがあって、それが勝敗に影響した
ケースは、他には1件のみである。
それに、後で転覆したチームにヒヤリングしてみると、
その原因は、より速いターンを実施しようと、普段は
しない特別な措置をやったらしい。それが上手くいかず
コース取りと、漕手、舵手とのトータルバランスが乱れ、
体勢を崩して転覆してしまったそうだ。
まあ、その古豪チームが、「少しでも速く」と考えた
理由は推察できる。それは、その地元古豪チームは、
これまでの本大会での優勝・入賞回数が最多であって、
「地元最強」の称号を得ていたチームだからだ。
地元古豪チームが必死で頑張る程に、近年における本大会
はレベルが高い、それは数年前よりドラゴン専業チームが
多数本大会に参戦しているからである。
滋賀県の四天王(小寺、池の里、龍人、琵琶ドラ)や
地元若手強豪の「守のシルバニアファミリー」を初め、
他府県参戦ながらも本大会をホーム大会とする優勝経験
チームの「からしれんこん」、そして、「吹龍」や
「メタルスタイリスト」「ドリーマーズ」等と、多数の
ドラゴン専業チームによる競技志向の強い大会になりつつ
ある、この為、今年の本大会の評価では「競技志向」の
評価点を従前よりも加点している。

専業チームが多数参戦している事により、地元系ビギナー
チームが手も足も出ない事である。これだと地元系チーム
は大会への参戦意欲を失ってしまうリスクもある。
本大会は数年前まで「実力別カテゴリー分け」であったが
何故か現在は1カテゴリーに1本化されてしまっている。
もしかすると運営側(自治体である)が、参戦チームの
実情に詳しく無いのかも知れない、すなわち「専業チーム
とは何か?」という点だ。
ここを理解すれば、従前のように「実力別カテゴリー分け」
に戻す方がベターであるという選択になるだろう。
まあでも、本大会は長い歴史を持ち、カテゴリー分けの
変遷も何度かあったので、少し遅れるかも知れないが、
その時代の状況に応じたカテゴリー分類に、また変化する
かも知れない。
----
では、次の優良大会。

競技志向 :★★★★★
大会環境 :★★★★
エンジョイ度:★★☆
観戦の楽しさ:★★★★☆
総合評価 :4.0
JDBA(日本ドラゴンボート協会)、SDBA(滋賀県ドラゴン
ボート協会)主管。大阪府ドラゴンボート協会協力の大会。
例年、雨天になりやすい(その率は6割程)大会であるが
今年もまた、台風の影響で一時的な豪雨に見舞われた。
ただまあ、幸いにして中止や中断となる状況では無く、
雨天を吹き飛ばすほどの熱戦が行われた大会である。

すなわち、現代の国内ドラゴン系大会で最も競技志向の
強い大会であり、遠く、熊本、沖縄、そして海外を含め
各地から超強豪チームが集結する。
ドラゴンはプロ競技とは異なり、「ランキング制度」は
無いのだが、もしそれを実施すれば、本大会は間違いなく
現在のドラゴンチームでのトップ(高)ランカーによる
頂上決戦と見なす事ができるであろう。

本記事冒頭写真)よりも、本大会の方が競技志向が高い
のは、日本選手権は20人漕ぎである為、現代の世情に
おいては、20人もの主力漕手を集められるチームは
少ないからだ。
つまり、20人漕ぎはエントリー(参戦)自体の敷居が高い。
対して、10人漕ぎの本大会は、遠距離参戦等においても
チームの負担が若干少なく、主力漕手も集め易い。
それと、もし20人以上もの漕手を集められる大勢力の
強豪チームであれば、本大会では、10人毎に分割して
エントリーすれば良い訳だ。
本大会に(超)強豪チームが集まり、競技志向が高まる
理由は上記の通りである。
----
ところで、上記、高島ペーロンやスモール選手権での
「専業チーム」という扱いの話であるが、これらは
勿論「アマチュア」なのだが、一般的に想像するような
「プロ」と「アマ」の区分は、ドラゴン競技においては
適用されない。
以下、長い余談となる。
まあ、多くのアマチュア(スポーツ)競技の運営側は、
自治体や地元団体(商工会等)や地元企業等が主体と
なって行っているケースも多く、そこでは、参加選手
(チーム)は「全てアマチュアである」という認識で
あろう。
だが、いわゆるドラゴンで言う「専業チーム」に当たる
ような、日常的かつ専門的に、その競技の練習を行っていて、
もしその競技がプロ化すれば、すぐにでもプロチームとして
やっていけるような高いスキルを持つ、セミプロ層または
ハイアマチュア層が多数存在する状況自体には、地方大会等
の運営側の多くは気づいていない。
つまり、「世の中にはプロとアマチュアの2種類しか無い」
と思い込んでいる訳だ。
では、プロとアマの差は何か? ここが世間一般では
大きくカン違いをしている事だろう。世間の一般層では
プロとは「それを生業としてお金を稼ぐ人」と思っている
のかもしれないが、たとえば一部のドラゴンやペーロン
競技でも、勝てば賞金は出る、ただ、その賞金だけでは
生計が立てられないから、他に本業を持っているだけだ。
それは、プロ競技が存在する野球やゴルフその他でも
同様であり、アマチュアでも出場できるオープン大会に
出て、賞金を貰えばプロなのか? いや、そうでも無い
何故ならば、それだけでは食べていけないからだ。
であれば、「本業としているか否か?」がプロの定義か?
いや、それも不自然であり、例えば陸上競技の日本代表等で
企業に所属しながら、その競技を続けていたら、その競技
そのもので収入を得ている訳では無い、だからそれをプロと
呼ぶのは微妙だ。(注:「社会人」等と定義する場合もある)
すなわち、「お金を貰っているかどうか?」や「本業と
しているかどうか?」では、プロとアマの区別はつかない。
・・と言うか、世の中でのスポーツあるいは仕事において
そうした上記の定義での「プロ」と「アマ」のどちらにも
属さない人たちが沢山居る。いやむしろ、それが大多数で
あって、例えば、ゴルフの大会の賞金だけでやっていける
選手等は、ほんの一握りであり、他の仕事の収入で食って
いくしか無い訳である。あるいは音楽の世界でのバンドや
歌手でも同様の状態だ、たまにはステージに立つのだが、
それだけでは食べていけない人達が大半である。
また、それらの「腕前」や「スキル」も区別には無関係だ、
「歌が上手ければ即、それはプロである」とも言い切れない。

スポンサー(企業や店舗等)が付いている、そこから
お金を貰えるならば、それはプロなのか? いや、そう
単純な話でも無いであろう。
あるいは、アマチュア劇団が、有料の入場料で、多数の
観客を集めて、お客を感動させる絶妙な演技を行ったとして、
だからそれはプロ劇団なのか? いや、何とも言えない。

世間一般の視点(定義)では、プロとアマの区別は曖昧だ。
よって、世間一般で言うプロとアマの定義は成り立たない、
では、どのように区別するべきか?
私は、プロとは「その仕事やパフォーマンスを、観客や
ギャラリー等に対して「魅せる」事が出来、その結果
として「対価」を得ようとする/得る事が出来る人達」
と定義している。ここに、運動能力や技能や技術や才能
やセンスや、弁舌や歌の上手さ等は、あまり関係が無い。
つまり、その人が行う行為が「お客さんの方を向いている」
人達はプロであり、「(お金を払う)お客さんの方を
向いていない(=自己満足である)」人達はアマチュアだ。
極めてシンプルではあるが、これが真理である。だから
いくら演奏が非常に上手な音楽バンドであっても、あくまで
「オレのギターは上手くて格好いいんだ、オレの音を聴け!」
という感じのパフォーマンスでは、それが有料ステージで
あったとしても、プロとは言い難い。
つまり、世の中にはセミプロ級の人達が沢山居る訳だから、
そういう風に、その競技や芸術・芸能等に真剣に向き合う人達と、
そうでは無い人達との差異は、世の中が思う「プロとアマの差」
としての間違った定義よりも、それよりも、ずっと大きい。
つまり「好きこそものの上手なれ」を地で行く話であり
自分が好きで、その分野をずっと続けているならば、
下手に向上心等の無い、世間で言うところのプロよりも、
ずっと実力的には上回るケースが良くある訳だ。
あとは、その実力者・猛者達が「お客の方を向けるか否か」
そこが真のプロとして通用するかどうかの境目だ。
ドラゴン競技がプロ化できるか否かも、実はそこにかかって
いる。大会や競技体系全体を運営する為には、その費用を、
スポンサーや選手達自身から得るのではなく、その大半を
観客やファン層からの収益で得なければならない、そして
現代においてプロ競技として成り立っているものでは、
必ず、そのビジネスモデルが成立している。
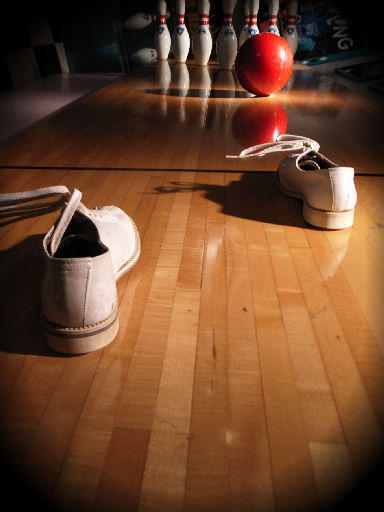
も、その競技が大流行していた時代(1970年前後)では
プロ化もされ、美人女子プロボウラーや、驚異の高得点を
叩き出す男性強豪ボウラーが人気で、TV中継もされていた。
しかし、後年にボウリングブームが去り、TV中継も無くなり
ボウリング場も減り、大衆の誰もがボウリングの事を忘れて
しまうようになっていくと、プロ競技の体系を維持する事が
難しくなる。
そこで、近年においては「P☆League」(Pリーグ)という
スタイルに転換し、またそこではプロ競技としての体系が
成立している。
「P☆League」とは、かつてのボウリングブームの際には
国民の誰もが知っていた(野球の「王貞治」氏よりも一般
知名度が高かった)美人女子プロボウラーの「中山律子」さん
(現:日本プロボウリング協会名誉会長)等により立ち上げ
られた「興業的」な主旨が非常に強いボウリング競技だ。
このPリーグは女子プロボウラーが主体となるリーグ戦で
優勝とかランキングとか、そういう点では一般的なプロ
スポーツ競技と同様だが、女子選手たちのコスチュームが
物凄い。まるで「コスプレか?」と思うような派手な衣装
に身を包み、かわいい(注:「プリティー」がPリーグの
Pの意味の一部となっている)女子選手達が、その外見に
まるでそぐわない剛速球や、強烈に曲がるカーブの球を
投げてストライクを連発する、という「ギャップ萌え」の
競技である。
ここでは勿論、その選手達の視点は100%観客を向いている。
何も、普通に競技をやるだけならば、派手なコスプレは
不用であろう、それは全て「観客を魅せる」為なのだ。
そう、本競技の立ち上げに尽力した「中山律子」プロは、
かつて、その競技自体の実力値(300点パーフェクトを
出している)も、さる事ながら、その美貌に注目されて、
TVの視聴者を釘付けにしたり、TV CMに出演したりで、
知名度を大幅にアップし、その結果として、世間での
ボウリングブームを大幅に加速し、各ボウリング場では
数時間待ちとなるほどのフィーバーを起こした。こうした
まさに時の人であったから、競技自体の実力値を高める事と
同等か、むしろそれ以上に「観客を魅せる事」の重要さを
よく認識しているのであろう。
大変余談が長くなったが、これは将来において、ドラゴン系
競技をプロ化したいと考える際に、非常に重要なポイントと
なる事だ。
つまり、プロ化するならば
「常に観客の方を見る事、魅せる事」
「観客に対し、「お金を払ってでも競技を見たい」という
パフォーマンスを実現できる事」
「観客に人気が高い、スター選手、スターチームを作る事」
あたりが、非常に大事である。
しかし、残念ながら現在のドラゴン系チームにおいて、
こうした視点で競技を行っているチームは皆無であろう。
逆に言えば、それ故にプロ化は難しい、とも言えるのかも
知れない。
観客の集客も課題だ、日本選手権や相生ペーロン等では
一般観客も多いが、すべてフリー(流れ)の観客であり
競技自体のファン層、というものは、殆ど存在していない。
チャンスがあるとすれば、この競技がメディアに注目
されるような、なんらかの出来事があった場合なのだが、
仮に世界大会等で優勝したりして、マスコミに取り上げ
られたとしても、チームや選手達が、アマチュア目線で
観客や大衆の方を向いていなければ、それは単なる
「一過性のニュース」で終わってしまう。
実際、ブレイクのきっかけがあった他のマイナー競技も
過去にいくつかあったのだが、残念ながら選手達や協会の
視点がアマチュア目線であったので、それらのマイナー競技
がプロ化される(つまり、ビジネスとして成り立たせる)
動きはあまり無かった。
現代においては、「スポンサー」は、単にお金を出して
くれる資産家や金満家等では無い。彼らは、その競技が
成長し、将来的に自身に利益をもたらしてくれると判断
する場合にのみお金を出す。すなわちそれは「投資」であり
決して「今、広告をするからお金を出してくれ」という
交渉が成り立つ訳では無いのだ。
(参考:昔の時代での芸術家に対する「パトロン」という
感覚であろう。パトロンは売れない絵描きなどの才能に
目を付け、生活を支援しつつ、後年に、有名になって
価値が上がった、その画家等の絵を高く販売する)
現代のネット社会では広告ビジネスモデル(アフィリエイト)
が全盛であるが、このビジネスモデルは未来永劫に成り立つ
訳では無い。仮に広告を出す場を動画サイト等の人気サイト
で作り上げたとしても、その広告による宣伝効果があって
実際に商品やサービスが売れて、広告主の収益が向上しない
限りは、無駄な広告や出費となってしまう訳だ。
(だから、近年のTV CM等では、効果が少ないから広告主が
減り、たいてい同じ企業ばかりがCMを流している。
流しすぎで、そればかりにお金を使っている悪印象もある
位なので、賢い消費者では「TV CMを行っている企業の商品
は購入しない」という選択をしているケースも多々ある)
よって、近未来の収益構造においては、ファウンディング
(投資型、資金調達型)のモデルが主になると予想できる、
これは、その競技、個人、事業、物品等において、
「今、お金を出しておけば、将来により大きい収益がある」
という観点である。(前述の「パトロン」も同じ)
事実、美術品とかカメラ等でもそうだが、投機型の商品は、
非常に高額で取引される。その理由は、その商品そのものに
それだけの高い価値があるからでは無いだろう、
「それを買えば、将来にさらに値上がりして高額に売れる」
(と考える)からである。
まあ、そういってしまうと身も蓋も無いが、要はその
商品、事業、個人、作品、競技等に将来性があるから、今、
その分野にお金を出して育て、将来での回収を狙う訳だ。
極めて余談が長くなったが、ここは現代社会を理解する
上で非常に重要な事だ。

有力なスポンサー(広告主)を探せば良い訳では無い。
まず、選手達が「観客を魅せる」競技として意識改革を
行い、その上で、この競技が将来的にビジネスとして
通用する事を見越した投資家にプレゼンして資金調達を
行う必要がある。つまりここでも「お客目線」が必要で
あり、ここで「お客」(=金を出す人)のスポンサー自体も
儲かる、Win-Win関係を提案していかなければならない訳だ。
簡単な話では無いが、今のままドラゴン競技を続けて
いても、年々運営が苦しくなってくる可能性もあり、
それでは選手達の大会参加料は値上げしていくばかりである。
事実、2021年の「ワールドマスターズゲームス関西」
でのドラゴン競技の参加料は1人あたり15000円と高額だ。
別競技では、マラソン等の参加費は2~3万円となる場合も
あると聞く、これが、アマチュア競技を自己資金で
運営する場合の実情であり、これでは選手達も、そう
簡単には各大会にエントリーできなくなってしまう。
そうならないようにするには、競技自体をプロ化して、
「お金を払って参加する」のではなく、「お金を貰って
参戦する」に変えていく必要がある。しかしそうなった
としても、アマチュア目線で「お金が貰える、ラッキー」
と思うようではプロにはなれない。プロとして通用する
為には、「観客たちを魅せて、そこからお金を貰う」
という視線が必要なのだ。人気商売とも言える訳だから
自身が速い(良く漕げる)というだけでは通用しなくなる。
長い余談となったが、とても重要な事だ。
今すぐに、どうのこうの、という話では無いが、将来的に
ドラゴンやペーロンをプロ競技化したいのであれば、
こうした様々な事を考慮する必要があり、かつそれは
競技の運営側だけが考えるものではなく、競技に参戦する
選手側においても、様々な「プロ」としての意識改革が
必要になる、という点が重要だ。
----
さて、では、3つ目の優良大会。

競技志向 :★★★
大会環境 :★★★★★
エンジョイ度:★★★★
観戦の楽しさ:★★★☆
総合評価 :3.8
主催、関西エアポート株式会社(KIXと伊丹を運営)
JDBA(日本ドラゴンボート協会)主管、和歌山ドラゴン
ボート協会協力の大会。
今年で16年目を迎えた長寿大会である。
長い余談を前述した「スポンサード」という点では、
非常に参考になるのが本大会であり、本大会には多数の
有名企業や大企業が、なんらかの形でスポンサーと
なっている事は、特筆すべき特徴である。
本大会においては、VIP専用とも言える「特設観覧席」が
存在している。そこで、大会運営側の関西エアポート社と
他のスポンサード企業と、どんな話が行われているのかは
知らない。でも、結果的に、その特設観覧席が設置された
以降では、有名企業等のスポンサーが増えているのだ。
2018年に最初にその特設観覧席が設置された際、一部の
選手達の間では、「あの観覧席、大会の後では壊して
しまうらしいよ、勿体無いね」という話が囁かれた。
だが、壊してしまったとしても、その投資効果は抜群だ、
その存在によりスポンサードが多数増えているならば、
むしろ、どんどんやるべきなのであろう。
私は、これを「秀吉の一夜城」方式と呼んでいる。
それは戦国時代、攻城が難しい敵方の堅固な城の目前に
短期間で仮の城を築城し、それにより敵方の戦意を
削いで、講和や攻城に持ち込む特殊な心理戦術である。
KIX大会での「一夜城」が、実際にどのような効果が
あって、どのような営業交渉が行われているのか、
までは良くわからない(知りようが無い)
勿論、関空側のスポンサード交渉の上手さもあるだろう。
ただまあ、非常に参考になる「プレゼンテーション」で
あるとも言える。現代における様々な営業・IRなど
に係わる商談や交渉では、こうした個性的かつ切り札的な
手法が有効であろう事が如実にわかる方法論だ。
前述しているドラゴン競技のプロ化の際には、重要な
参考事例として、学んでおくべき内容だと思う。

の評価点が5点満点である。交通の便、駅近の会場、
多数のスポンサードにより近年では極めて整備された
大会観戦設備、そうした点がとても優秀である。
その結果として、大会の雰囲気も良い。幸いにして
競技志向もあまり高く無い為、スポンサー企業チーム
等でも、稀に決勝戦とかに進出して大いに盛り上がる。
結果として大会全体の「エンジョイ度」も好評価だ。
また、ビギナーチームの比率が高い事は、むしろ
競技志向よりもエンジョイ度を優先するという、本大会
の方向性やコンセプトに、とてもマッチしている。
専業チームの参戦数が減っているのは、本大会が、現在
では希少な20人漕ぎを主体とした大会であり、専業チーム
の現状では、20人の漕手を揃える事が難しいからだ、
しかし、現在ではそれがむしろ良い結果に繋がっていて、
関空関連、スポンサー企業関連、自治体関連等の多数の
ビギナーチームが、純粋に競技を楽しめる環境が構築
されている。
ビギナーチームの多くは若い選手達で構成されていて、
一流企業や自治体等での美人選手も多い状態だ。
男性層の生涯未婚率が増えてきていて、社会的にも問題
になりつつある(例:高齢化社会となる)現代の世情では、
仮に本大会を「婚活」の場とする事も、決して「不謹慎だ」
とは言い切れないようにも思える。
で、この大会で、専業チーム等が「必死のパッチ」で
漕いでいるのは、やや違和感もあるような様相になりつつ
ある状態であり、本大会では、ある程度は、スポンサード
となっているような運営関連のチーム達に楽しんでいただく
事も考えるべきであろう、そうしたスポンサード企業群が
無ければ、大会自体の開催も危ぶまれてしまうのだ。

惜しむらくは、国内の選手達も、もっと積極的に
海外チームと交流を図るべきであろう、海外の人達と
しゃべり放題という、こんな素晴らしい機会は滅多に
無いのだから・・
----
では、4つ目の優良大会。

競技志向 :★★★☆
大会環境 :★★★☆
エンジョイ度:★★★
観戦の楽しさ:★★★★
総合評価 :3.5
びわこペーロン実行委員会(びわこ放送、滋賀県ドラゴン
ボート協会等)主管の大会。
本大会は、少々アンバランスな課題がある大会だ。
およそ10年ほど前までは、本大会は地元のお祭り的な
様相の強い大会であり、いや、むしろ滋賀県に多数ある
大企業における「福利厚生」を主眼としていた大会で
あったとも言える。(つまり、社員レクレーションだ)
ところが、10年程前から、この大会を「競技」と見なす
ドラゴン専業チームが多数参戦を開始、すると当然ながら
全カテゴリーの上位チームは全てドラゴン専業チーム一色
となってしまい、全く手も足も出なくなった地元企業系
ビギナーチームからは「プロ(と彼らは思っている)の
チームがこの大会に参加するのは不公平(場違い)だ」
という不満が多く出るようになってしまった。
すぐさまカテゴリー分けを見直し、専業チーム群を
競技専用カテゴリーに封じ込めてしまえば良かったのだが
例によって、そういう抜本的措置は担当者が頻繁に変わる
地方大会では難しい、基本は、前年までのやり方を踏襲
せざるを得ないからだ。
数年前までは「このままでは大会の主旨が崩壊する」と
私は懸念を強く持っていたのだが、まあ、とは言え、
ドラゴン専業チームには責任は無い、あくまで彼らも
お金を払って大会に参戦する「お客様」なのだ。
まさか「ちょっと地元に気遣って、手を抜いてください」
などとは言う訳にはいかないだろう。
「遅いのは練習不足だからだ、我々はちゃんと練習して
いる、だから速いのだ」という論理で一蹴されてしまう。

企業チームの一部が、そうしたドラゴン専業チームに
触発されて、かなり本格的な練習を重ねるようになって
きているのだ。
つまり彼らは、「専業チーム」の何たるかを理解し、
「それに勝つには、自分たちも多数の練習を重ねるしかない」
という事に気づいたわけだ。
一部の企業チームは、専業チームに倣ってカーボンパドルを
装備、そのチーム数は年々増えていて、今や、地元強豪企業
チームの殆どはカーボンで武装している。
また、専業チームがプロチームでは無い事を理解した
企業チームの一部は、OPAL等の練習場で、専業チームからの
厚意での直接指導を受け、その実力値を高めている。
今年2019年では、最も地元チームの入賞が困難な競技志向
の極めて高い「20人漕ぎ一般」の部で、ついに地元チーム
「シンコーメタリコン」(企業系)が3位に初入賞。
これまで約10年間は、全て入賞は専業チームだった訳だ。
こういう動向となるのであれば、あえて「チャンピオン
リーグ」等の「専業チーム専用カテゴリー」を設置する
必要は無いかも知れない、専業チームは、うまく地元チーム
に良い影響を与え、ドラゴン競技の育成に寄与している
からである。
まあただし、全ての地元チームがそうである訳でも無い、
依然、本大会は企業の福利厚生での「夏のレジャー」であり、
競技とかでは無く、純粋に大会を楽しみたいと思う参加
選手達が大半(およそ7~8割)なのだ。
その微妙なバランス感覚を意識した上で、ドラゴン専業
チームは、本大会に参戦し、競技自体の育成に少しでも
配慮していただければ幸いだと思う。
----
では、ラストの優良大会。

コンテスト(大阪府・高石市・大阪府立漕艇センター)
競技志向 :★★☆
大会環境 :★★★☆
エンジョイ度:★★★☆
観戦の楽しさ:★★★☆
総合評価 :3.3
地方協会による小規模大会である。
以前は、「大阪府民体育大会」という名称であり、
これは大阪府全体の体育協会に加盟する各競技団体が
少なくとも年に1度は、その競技を実施する事が
必要とされている。
で、2020年の東京オリンピック開催を機会に各地の
様々な団体・行事での「体育」という名称が「スポーツ」
に改められていく状況がある模様である。
いち早く、本大会も「大阪府民スポーツ大会」となり、
来年2020年は、従前の「体育の日」は「スポーツの日」
と名称変更し、オリンピック開会式の日(7月24日)
に変更され、前日の「海の日」と合わせ4連休となる。
(注:2021年からは「スポーツの日」は従前の
「体育の日」と同じ、10月第二週月曜日に戻る)
さて、本大会を取り上げたのは、別に「スポーツ」に
名称変更されたからでは無い。
本大会では史上初の「舵取りコンテスト」が行われた。
この歴史的価値を鑑みての、ベスト大会選出である。
そういう意味では、今年静岡県御前崎市で実施された
「ドラゴンボート・パワーバトル」(一種の綱引き競技)
も、歴史的価値が高い大会であったと思う。
ただ、開催日(会場)の都合で、その大会は、前述の
びわこペーロンと同日開催となってしまい、私も御前崎へ
観戦に行けなかったし、逆に静岡県のチームも、琵琶湖
に来る事ができなくなってしまっていたので紹介困難だ。
別の日に開催できるならば、それを希望する次第である。
ちなみに、鳥取の「東郷湖大会」も例年、びわこペーロン
と同日開催になっていて、そちらも一度も観戦に行けて
いない次第だ。重複日大会開催は、私ならずとも、参戦
チームにも迷いが生じるだろうし、いろいろと会場の
都合はあるだろうが、できれば重複しない方が望ましい。

チーム毎のタイムを重要視するのではなく、舵手の
技能を競うスラローム型のタイムレースである。
漕手・鼓手については、舵手による自由裁量だ、
それらの人数を舵手が自由に決める事が出来るという
特異なレギュレーションである。
漕手を増やせば、速くはなるが、舵による操船が難しい。
その逆は、軽くなり操船が容易だが、遅くなる。
鼓手を外せば軽くはなるが、漕手のペース管理が困難だ、
これらを上手くバランスさせる手法は、まだ今回の
大会が第1回目なので、セオリーが組み上がっていない、
今後、経験的に「鉄板」の方法論が出来てくるであろう。
で、何故こうした試みが行われるか?、については、
これは各地のチームや協会でも課題となっている
「慢性的な舵手不足」である。
そもそも、ドラゴン(ペーロン)選手の多くは、
「漕ぎたい」から競技を行っている訳であり、舵手の
なり手(希望者)は、とても少ない。
それに加えて、舵手には高い技量が必要とされる、
また、責任の重いポジション(例:舵手が艇を曲げて
しまえば、即、そのチームは敗退だ)でもあるから、
そう簡単に漕手から舵手への転向も困難である。
よって、「舵手の育成」を主眼としたのが、本大会の
舵取りコンテストである。
その効果は早速少し出てきていて、コンテストへの
挑戦者は、普段からの舵手では無く、チームの漕手で
あるケースも何人か出てきている。

大会において、是非、同様な試みを行う事を推奨したい、
どの地区やチームにおいても「舵手の不足」は深刻な
問題であろうからだ。
----
さて、本記事はこのあたりまでで、次回も総集編として
「ベストチーム編」を書く事にする。