高いコストパフォーマンスと付随する性能を持った優秀な
写真用交換レンズを、コスパ面からの評価点のBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回の記事がシリーズのラストで、BEST4の紹介となる。
これらを順に紹介して行こう。
(ランキングの決め方は第1回記事を参照。
なお、評価得点が同点の場合は、適宜順位を決定している)
---
第4位
評価得点 4.45 (内、コスパ点 5.0)
![c0032138_21343464.jpg]()
レンズ購入価格:1,000円(中古、ジャンク品)
使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)
1970年代のMF単焦点望遠レンズ、M42マウント。
購入価格が極めて安価なのは、「小カビ」によるジャンク品
であるからだが、仮に程度の良い個体であったとしても
4000円前後の中古相場なので、あまり高価なものでは無い。
![c0032138_21343586.jpg]()
販売台数があったM42マウントMF一眼レフ、PENTAX SPシリーズ
の最終時期のカメラ用の交換レンズだ、しかも望遠としては
比較的定番の200mm/F4、十分な販売数があったのだろうか・・
今なお中古市場では入手はさほど難しく無い状況だ。
本シリーズ記事では、現代の中古市場で「入手不能」や
「入手困難」のレンズはランクインさせない事になっているが、
本レンズであればギリギリセーフであろう。
M42マウントのレンズは、およそ殆どの一眼レフやミラーレス機
にアダプターを用いて装着が可能だ。
本レンズを使う際、いつもは望遠である特徴をより強調する為に、
μ4/3機、特に「望遠母艦」であるLUMIX DMC-G5かDMC-G6あたり
を持ち出す事が多いのだが、今回はちょっと捻って、FUJIの
Xマウントの機種だ。ここで使っているM42→Xアダプターは、
テイルト型アダプターなので、本レンズを使って「アオリ効果」
を得る事も出来る(が、重いレンズなので使いにくかった)
本シリーズに、こうしたオールドのMF単焦点レンズが登場する事は
珍しい(SMCT55mm/F1.8以来)のだが、まあ本レンズの性能と
価格(1000円)という事からのコスパ点(満点)は、やはり圧倒的
であり、コスパランキング上位に入ってくる事は確かであろう。
(本記事では、もう1本オールドの単焦点がランクインしている)
なお「200mm/F4というレンズなんて、いくらでもあるじゃあ
ないか、何故このレンズが選ばれているのだ?」というマニア層
からの疑問もある事であろう、まあ、確かにそう思うかも知れない。
だが「ミラーレス・マニアックス」の過去シリーズ記事でも
何本もの同時代(1970~1980年代)の、200/4級、200/3.5級
等の単焦点レンズを紹介しているのだが、それらと比べても、
やはり本レンズの方が高い描写力があると思う。
(いずれ「特殊レンズ超マニアックス」記事で、「オールド
200mm」単焦点レンズの特集を組む予定だ)
その描写力の高さが、本レンズの長所である。それは半世紀近く
も前に作られたレンズとは思えない程だ。
特にボケ質が良い。撮影条件によってはボケ質破綻が若干出るが
絞り値の変更程度で概ね回避できると思う。
(上の紅葉の写真のボケ質は良いが、下の野鳥の写真では
ボケ質破綻が若干見られる)
ただし、ボケ質破綻の為に変えれる絞り値の実際の可変範囲は
望遠効果を維持したい、という意図においては狭く、実質的には
F8位までの、計3~4段階しか無いであろう。
ちなみに、本レンズの絞り環は1段と半段の複合型となっている
珍しい仕様で、具体的にはF値が変更可能なクリックストップは、
4,5.6,(6.7),8,(9.5),11,(13),16,22 となっている。
例えば、()で示されたF(6.7)などは中間絞り値であるのだが、
何故か、F4とF5.6の間には、中間絞り(F4.5)位置が無い。
![c0032138_21343488.jpg]()
200mmレンズにしてはやや長く、不満を感じる事だ。
ただ、この点については、今回使用のシステムでは無理だが、
「ヘリコイド付きアダプター」を使用する回避方法がある。
なお、これも今回使用のX-T1では無理だが、デジタルズーム機能
を搭載している機種であれば、見かけ上の撮影倍率を上げる事は
可能だ。しかし、デジタルズームを使ったとしても最短撮影距離の
長さは変わらないので、寄って写せないから撮影アングルやレベル
(=撮影する為の高さ、例:アイレベル、ウエストレベル)は
制限が大きいままだ。
余談だが、デジタルズーム機能を画質劣化や画素数減少の理由で
嫌う風潮があったり、搭載されていないミラーレス機もあるのだが、
デジタル(スマート系)ズームは、ボケ量やボケ質を維持したまま
構図変更が可能な便利な機能だ。なお、それが「トリミングと等価」
だと思うのであれば、これは実用的には、構図変化による輝度分布の
変化に露出計が追従する(露出補正や輝度レタッチの必要性が低下
する)機種も一部には存在する事と、後処理でのトリミングの
作業負担が減る事、すなわち「編集コストの低減」(ここで言う
コストとは、手間などの労力)の効果が大きい。
特に膨大な数の写真を撮った際などは、いちいちトリミング等を
後からはやっていられないのだ(まあ、ただしデジタルズームを
かけない方がトリミングの自由度は高いので、撮影者がどこまで
編集コストをかけられるのか?という点や、デジタルズームでの
構図を、トリミング後の構図として、ぴったりと決めれるか?
といった撮影者のスキル面にも依存する事であろう)
続く弱点だが、200mm単焦点の小口径(F4)版とは言え、
このレンズの重量は比較的重く、570g近くもある。
これだと今回使用のティルト型アダプターは構造が柔(やわ)
なので、使用する際に、この重さが多少不安だ。
![c0032138_21343436.jpg]()
印象があるのか? マニア層においては極めて人気が無い。
あるいは、本レンズよりも後のAF/デジタル時代においては、
200mmという焦点距離は、望遠ズームに内包されてしまい、
単焦点のレンズは初級中級層に対しては「使い難い」という印象を
与えてしまうのか? ともかく、どのユーザー層にも不人気であり
その結果としての中古相場は極めて安価なのだが、それがまた
「安かろう、悪かろう」という印象(誤解)に繋がっていく。
こんな状況なので、およそ、このクラスのレンズをまともに買って
評価した例は少ないだろうし、真の実力値も世に知られる事が無い。
しかしながらMF時代の200mmのF4級では本SMCT200/4は良く写り、
MFのF3.5級でもMINOLTA MC TELE ROKKOR QF 200mm/f3.5
(ミラーレス・マニアックス第68回記事)等も、かなり良く写る、
F2.8級だとAF時代のMINOLTA APO HI-SPEED AF200mm/f2.8
(本シリーズ第4回記事)は素晴らしく良く写るレンズだ。
200mm単焦点という、ありふれたスペックのレンズの中にも、
こうした名レンズが眠っている事が多い。
そういう「掘り出し物/お宝」を発掘する事も、またマニアックな
楽しみ方になるのだと思う。
本SMCT200/4は、もし1000円とか2000円で見かけたら、迷わず
買ってみるのが良い。試写した際、その高い描写力と圧倒的な
コストパフォーマンスに、きっと驚きを隠せない事であろう。
「ならば、高価なレンズって、何の意味があるのだろう?」と
疑問すら感じてしまうかも知れない、それもまた、見聞・見識を
広めるという意味では重要な事だと思う。
---
第3位
評価得点 4.55 (内、コスパ点 5.0)
![c0032138_21344578.jpg]()
レンズ購入価格:2,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第2回記事で紹介の
1970年代のMF小口径標準レンズ。 ミノルタMC/MD系マウントだ。
当該名玉編記事では、第11位相当にランクインしたが、
コスパ点が満点の5点であった為、本シリーズ記事では、
コスパを重視する採点手法であり、第3位までランクアップした。
![c0032138_21344443.jpg]()
小口径標準である。初級層あるいは初級マニアであれば、
「他に、F1.4やF1.2の高級な標準レンズがいくらでもあるのに
何故このレンズなのだ?高いレンズの方が写りが良いだろう?」
という疑問があると思う。
しかしこれがまるっきりの誤解なのだ、私は50mm級標準レンズを
何十本も所有しているが、MF時代~AF時代~デジタル初期の時代
にかけ、F1.2~F1.4級の50mm「大口径」標準レンズと、
F1.7~F2.0級の50mm「小口径」標準レンズが、同一マウントで
併売されていた場合、ほぼ必ずと言っていい程、小口径版の方が
写りが良い。
大口径版は、確かに明るいし、ボケ量も多くとれる、そして必ず
小口径版より高価だ。だから普通はそちらの方が良いレンズだと
思い込み、写りも良いものだ、と信じて疑わない。
まあでも、それは事実では無い。
そして、もし安いレンズの方が、価格の高いレンズよりも性能が
高い、となってしまったら、レンズの商品ラインナップ上も
不自然な事になってしまうかも知れない。
![c0032138_21344433.jpg]()
50mm「小口径」標準の方に「性能制限」をかけていた事もある。
具体的な例をあげれば、50mm/f1.4の最短撮影距離は45cmだが、
50mm/f1.8の最短撮影距離を60cmに制限する、などである。
この性能差があれば、近接撮影時において、F1.4版の方が
遥かに被写体深度を浅くする事ができる、つまり「良くボケる」
メーカーあるいは、その営業マンとしては、ユーザー層に対し、
「ほらね、こちらのF1.4版の方が良く背景がボケるでしょう?
だから、こちらのF1.4版の方が値段が高いのですよ」
という理屈を、初級中級層に対して言えるのだ。
(ちなみに、本MC50/1.7も最短撮影距離が50cmと、F1.4級の
45cmに対し、ほんの5cmだけ寄れない仕様となっている)
だけど、こういう風に、メーカーの都合で、低価格商品に対して
差別化する事は、個人的には「好ましく無い」と思っている。
最短撮影距離の件ではなく、カメラにおいても性能を出し惜しみ
する例は、その後のAF/デジタル時代での普及版(低価格)一眼レフ
においても、非常に良くあった(例:普及機は連写速度が遅い等)
のだが、まあ、あえてそういった機種は買わないようにしていた。
性能・スペックに関する資料を良く読み込めば、そうした「仕掛け」
があるだろう事が想像できるからだ。
メーカー側の「売りたい」という気持ちと、ユーザー側の「買いたい」
という心理をバランスさせるのは、一種の「勝負である」と
私は思っている。つまり、値段と本来の絶対的価値が見合わない物
(=コスパの悪い物)を買わされてしまったら「ユーザー側の負け」
だと私は思っている訳だ。
![c0032138_21345743.jpg]()
に中古市場で流れていた、一種の「処分品」である、だから、
これの値段(2,000円)と、実際の価値は釣り合わない。
「釣り合わない」というのは良い意味の方であり、すなわち
コスパが極めて良い「お買い得品」であったと言う事だ。
「他にもMF50mm小口径はいくらでもあるだろう?何故この
レンズが選ばれているのか?」というマニア層の疑問に関してだが、
まず、確かにMF50mm小口径は色々あって、たいていそのどれも
が良く写り、しかも、それらの多くは安価な中古相場だ。
ついでに言えば、その殆どの小口径標準は、同じようなレンズ構成
で設計されていて、性能上の差も、あまり(ほぼ全く)出ない。
しかし、それでもたとえば、ニコン版のAi50mm/F1.8Sとか、
コンタックスのP50mm/F1.7とかは、中古相場が高価すぎるのだ。
(ブランド力が高い為、相場も高額になると言う理由だ)
それから、マウントの問題もある。
MF時代のマウントと現代のデジタル一眼レフのマウントにおいて
かろうじて形状互換性があるのは、NIKON FとPENTAX Kである。
(まあ、実際には形状が同じでも様々な使用制限は出てくる)
ミノルタMC/MDやキヤノンFDに関しては現代の一眼レフでの
使用は難しい、なので中古相場が安価になっていたのは当然だが
現代においては、ミラーレス機を用いることで、そうしたMDや
FDのレンズを何ら制限なく使う事ができるようになった。
![c0032138_21345659.jpg]()
安価である事は確かであり、まあ、それらの状況から、本レンズは
安価に購入でき、結果的に他社レンズよりもコスパが良い訳だ。
---
第2位
評価得点 4.55 (内、コスパ点 5.0)
![c0032138_21350613.jpg]()
レンズ購入価格:12,000円(中古)
使用カメラ:SONY α65(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第2回、ハイコスパ第10回記事
で紹介の、2010年代のAF単焦点準広角(標準画角)レンズ。
α(A)マウントであり、APS-C機専用の為、換算画角は
約52mm相当となる。
いわゆる「エントリーレンズ」である。
本シリーズ記事開始当初は「ランクインするのは、マクロレンズと
エントリーレンズばかりになってしまうのでは?」と危惧したが
ラストのBEST4に入ったエントリーレンズは、幸か不幸か本レンズ
のみである。
![c0032138_21350637.jpg]()
(高スペック)である事だ。
具体的には、まず、AFの35mm/F1.8(級)という仕様のレンズ
の中では本レンズが最も安価な事だ。
一般的には、一眼レフ用のAFレンズで35mmの単焦点では、
F1.4級の物はかなり高価であり、開放F値がそれより半絞り暗い
F1.8級の物も(特にフルサイズ用は)高価となる。
例えばタムロンのSP35mm/F1.8(F012)(レンズマニアックス
第13回記事等で紹介)の定価は9万円もする。
「このレンズは最新の高画質仕様だから高い」と言うならば・・
キヤノンのEF35mm/F2 IS USM(未所有)の定価が83,000円だ。
(注:旧型のEF35mm/F2は、ミラーレス第68回記事で紹介、
そのレンズは1990年の発売で定価38,300円であった)
「これもフルサイズ対応の高性能レンズだ」と言うならば・・
エントリーレンズのカテゴリーに属すると思われる、ニコンの
AF-S DX NIKKOR 35mm/F1.8G(APS-C専用、ハイコスパ
第26回記事)の定価が35,000円である。
対して、本DT35mm/F1.8(SAL35F18)は定価24,000円と
格段に安価である。(注:ここにあげた定価はいずれも税別)
なお、MFレンズであれば、中一光学のCreator 35mm/F2
(本シリーズ第4回記事)は、実売定価が約2万円と、さらに安価で
あるが、これは中国製のローコストレンズ(ただし品質や描写力は
悪くない)であるから、まあ例外的だ。
それから、「重要な仕様」は焦点距離と開放F値だけでは無い、
最短撮影距離だが、本DT35/1.8では驚異の23cmである。
近年に発売されたTAMRON SP35/1.8が最短20cmで、本レンズを
上回るまで、長らく本DT35/1.8が最も寄れる35mm単焦点であった。
(注:35mmマクロレンズや、オールド海外製レンズを除く)
あと、重量であるが、本DT35/1.8は170gと軽量だ。
比較をするのは少々可哀想だが、高性能レンズTAMRON
SP35/1.8(F012)は480g以上と3倍近くも重い。
なお、本レンズが軽量である事と引き換えに、作りがチャチ
(プラスチッキーで、安っぽい)と言う弱点を持つ。
![c0032138_21350758.jpg]()
値段を越えた仕様・性能を持つレンズという事であり、これが
すなわち「代表的なハイコスパレンズである」と言えよう。
なお、私の中古購入価格12,000円は、少し前の相場であり
やや高目だ、2019年現在では1万円以下の価格で購入可能
だと思う。
この値段でこの性能(仕様)であれば、ほとんど文句は無いとは
思うが、一応弱点をあげておくと、まず前述の作りの悪さ
(高級感が無く、安っぽい)と、描写力があまりスペシャルという
訳でもなく、まあ普通の写りのレンズである事だ。
寄れる(最短撮影距離が短い)のは良い事だが、被写界深度が浅い
写真を撮る際には、ボケ質の破綻にも若干注意しなければならない、
常にボケ質が良い写真が撮れると言う事でも無いのだ。
まあでも、「エントリーレンズ」という物は、基本的にどれを
選んでも後悔は無いであろう、なにせ、メーカーとしては、
それを「交換レンズのお試し版」として販売し、初級ユーザーが
それを気に入ってもらって、自社のより高価な、レンズやカメラ
本体の販売促進を目的としている訳だからだ。
もしエントリーレンズが不満足な性能だったら、それを買った
ユーザーは二度とそのメーカーの製品を買ってくれなくなる、
という、市場戦略上、極めて重要なポジションのレンズだ。
よって、価格を越えた性能がある事は言うまでも無い、すなわち
エントリーレンズは、どれも極めてコスパが良い訳だ。
![c0032138_21350623.jpg]()
持たない、「どうせお金を出すのであれば、最高性能のものが
欲しい」という考え方であろう。まあ確かに、本レンズには
超音波モーターは入っていないし、超高画素時代に対応した
最新の高解像力設計という訳でもない、そしてフルサイズ対応
でも無い。しかし、それらの「付加価値」が、そのユーザー層に
本当に必要なのかどうかは状況によりけりだ。
不要なまでのスペックのものを高価に購入する事は、結局は
「メーカーの利益」として還元されてしまう(=ユーザーの負け)
という事だ。
が、このあたりの判断はユーザーの志向や機材購入コンセプトに
よりけりだ、「無駄にお金を払いたくは無い」のか、あるいは
「お金をかけても最高のものが欲しい」と思うかは、ユーザー
個人の価値観にもゆだねられるであろう。
ただ、その「価値観」は極めて重要だ。良いモノと、そうで無い
モノを見分ける、あるいは自分にとって何が必要で、何が必要
では無いのかを見分ける力が無ければ、ユーザーの機材購入
コンセプトなんて、あって無いような事となってしまう。
事実、本レンズDT35/1.8は、最短撮影距離といった性能面を
とってみれば、全35mmレンズ中トップクラス(長らく1位)
であったのだ、同マウントでの高価な上位製品AF35mm/f1.4
(ミラーレス第60回記事)を、「何かを」期待して購入して
「思ったほど寄れない(最短30cm)」などと不満を言って
いたら、何をしているのかわからなくなってしまうであろう・・
まあ、そういう事が「価値観」に繋がるのだと思う。
---
さて、いよいよラストは栄光の第1位だ。
評価得点 4.75 (内、コスパ点 5.0)
![c0032138_21351752.jpg]()
レンズ購入価格:15,000円(中古)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回記事で紹介の
1980年代後半のAF標準等倍マクロレンズ。
ミノルタα→SONY α(A)マウント、銀塩時代のレンズであるがら
勿論フルサイズ対応だ。
![c0032138_21351774.jpg]()
SONY製50mm/F2.8Macro (SAL50M28)に繋がるが、約30年間
に渡り光学系に大きな変更は無いと思う。つまり「最初期型から
極めて完成度が高かった」と言う事であり、同じマクロレンズ
として完成度の高いロングセラー名玉TAMRON SP90mm/f2.8
(1996年の72E型より続く。本シリーズ第10回記事参照)
と肩を並べる歴史的名マクロレンズだと思う。
最初期型である本レンズの発売年度は不明だが、恐らくは
1980年代の後半、ミノルタα-7000(1985年、未所有)と
同時代だと思われる。このα-7000はAF一眼レフとしては
初の実用的カメラであり、市場全般に大きなインパクトを
与え、「αショック」と呼ばれた。
これ以降の各社のカメラ・レンズは一斉にAF化に追従、
1980年代後半では「AFにあらずんば、カメラにあらず」と
いう雰囲気が市場には漂っていた事であろう。
この「AF至上主義」は、交換レンズにもおよび、MFを軽視
あるいは無視した仕様のものもあった。
だいたい型番からして、α用の交換レンズは「AF何々」
という名称である。
![c0032138_21351629.jpg]()
極めて狭い。
つまり「AFがあるのだから、MFでは撮らないでしょう?」という
仕様になっていると言う訳だ、だが勿論、全ての撮影シーンで
AFが有効に機能する事は無い。マクロ撮影ならば、なおさらで
当時のAFの精度不足、測距点が少なく構図の自由度が無い、
等の問題により、「MFはやはり必要」という風潮になっていく。
その後の改良品(New型、D型、SONY型)では、バージョン
アップのたびに、MF時の操作性向上の為にピントリングの幅が
広くなっていく。
ばお、中古相場はバージョンが新しくなる程、当然高価になる、
最初期型の場合は、現代での相場は1万円以下であり、
性能からすると極めて安価で、コスパが最高レベルに高い。
(それ故に、本レンズもコスパ点は満点であり、描写力などの
性能を加味して、栄光の第1位となった次第だ)
![c0032138_21352595.jpg]()
使用している状態では実用的な面で大きな不満は無い筈だ。
まあ重箱の隅をつつくように言えば、解像力が低いとか
逆光耐性、ボケ質破綻、AF精度、などが上げられるが、
いずれも軽微なレベルであるし、30年以上も前のレンズと
思えば、やむを得ない節もある。
それに、もしこれらが重欠点であるならば、長い年月の間に
製品は改良されていく筈だ、その改良点が、少なくとも光学系
においては、ほとんど無かった、という状況が、すなわち
問題点には至らない、という事実を示している。
なお、こういうケースを鑑みて、私の場合は、一般的な交換
レンズ製品において、前モデルと後継モデルでの間で光学系の
変更が無かった際、その前モデルを「十分に描写力が高かった」
と判断して、優先的に購入する事としている。
新モデル発売により、前モデルの中古価格は大きく下落するのが
常であるので、極めてコスパの良い買い物が出来る訳だ。
![c0032138_21352524.jpg]()
ここまで色々なハイコスパレンズを紹介してきたのだが
「いくら安価にレンズを買っても、結局沢山買っていたら
コストがかかってしょうが無いじゃあないか?」という
疑問もあるだろう。
だが、私としては、「できるだけ沢山のレンズを知りたい」
という「探究心」もまた、1つの機材購入コンセプトとして
ある訳だ。まあ、なにかの方向性をもって突き詰める事が
「趣味」、あるいは「マニア道」としては、切っても切れない
重要な要素となる。
本記事の読者層としては、単純に「安くて良いレンズが知りたい」
というニーズがあるのならば、記事を読んで気に入ったレンズ
を探して買えば良い訳だ。そういうシンプルな話である。
注意点だが、機材の購入コンセプトが人それぞれであるならば
高コスパレンズを買ったところで満足できない人も居る、と言う
点だ。例えば、「いくら性能は良くても、こんな安っぽい作り
のレンズは嫌だ」という考え方を持っている人も居るであろう。
まあでも、人の「価値観」は変化する場合もある。
いままで「安かろう、悪かろう」と食わず嫌いをしていたのが
試しに買ってみたら、ハマってしまうというケースも有り得る。
でもまあ、それは悪い話では無い、価値観は変化しても構わない
訳だ。
結局、重要なのは、別にそれが変わっていっても良いのだが、
いかに自分自身の強い「価値観」を持つか、という点だと思う、
さもないと、「誰かが良いと言ったから買う」などと、
他人まかせの機材購入コンセプトしか持てなくなってしまうで
あろう、それは、一番やってはいけない事だと思っている。
以上で本シリーズ記事を終了する。
写真用交換レンズを、コスパ面からの評価点のBEST40を
ランキング形式で紹介するシリーズ記事。
今回の記事がシリーズのラストで、BEST4の紹介となる。
これらを順に紹介して行こう。
(ランキングの決め方は第1回記事を参照。
なお、評価得点が同点の場合は、適宜順位を決定している)
---
第4位
評価得点 4.45 (内、コスパ点 5.0)

レンズ購入価格:1,000円(中古、ジャンク品)
使用カメラ:FUJIFILM X-T1(APS-C機)
1970年代のMF単焦点望遠レンズ、M42マウント。
購入価格が極めて安価なのは、「小カビ」によるジャンク品
であるからだが、仮に程度の良い個体であったとしても
4000円前後の中古相場なので、あまり高価なものでは無い。

販売台数があったM42マウントMF一眼レフ、PENTAX SPシリーズ
の最終時期のカメラ用の交換レンズだ、しかも望遠としては
比較的定番の200mm/F4、十分な販売数があったのだろうか・・
今なお中古市場では入手はさほど難しく無い状況だ。
本シリーズ記事では、現代の中古市場で「入手不能」や
「入手困難」のレンズはランクインさせない事になっているが、
本レンズであればギリギリセーフであろう。
M42マウントのレンズは、およそ殆どの一眼レフやミラーレス機
にアダプターを用いて装着が可能だ。
本レンズを使う際、いつもは望遠である特徴をより強調する為に、
μ4/3機、特に「望遠母艦」であるLUMIX DMC-G5かDMC-G6あたり
を持ち出す事が多いのだが、今回はちょっと捻って、FUJIの
Xマウントの機種だ。ここで使っているM42→Xアダプターは、
テイルト型アダプターなので、本レンズを使って「アオリ効果」
を得る事も出来る(が、重いレンズなので使いにくかった)
本シリーズに、こうしたオールドのMF単焦点レンズが登場する事は
珍しい(SMCT55mm/F1.8以来)のだが、まあ本レンズの性能と
価格(1000円)という事からのコスパ点(満点)は、やはり圧倒的
であり、コスパランキング上位に入ってくる事は確かであろう。
(本記事では、もう1本オールドの単焦点がランクインしている)
なお「200mm/F4というレンズなんて、いくらでもあるじゃあ
ないか、何故このレンズが選ばれているのだ?」というマニア層
からの疑問もある事であろう、まあ、確かにそう思うかも知れない。
だが「ミラーレス・マニアックス」の過去シリーズ記事でも
何本もの同時代(1970~1980年代)の、200/4級、200/3.5級
等の単焦点レンズを紹介しているのだが、それらと比べても、
やはり本レンズの方が高い描写力があると思う。
(いずれ「特殊レンズ超マニアックス」記事で、「オールド
200mm」単焦点レンズの特集を組む予定だ)
その描写力の高さが、本レンズの長所である。それは半世紀近く
も前に作られたレンズとは思えない程だ。
特にボケ質が良い。撮影条件によってはボケ質破綻が若干出るが
絞り値の変更程度で概ね回避できると思う。
(上の紅葉の写真のボケ質は良いが、下の野鳥の写真では
ボケ質破綻が若干見られる)
ただし、ボケ質破綻の為に変えれる絞り値の実際の可変範囲は
望遠効果を維持したい、という意図においては狭く、実質的には
F8位までの、計3~4段階しか無いであろう。
ちなみに、本レンズの絞り環は1段と半段の複合型となっている
珍しい仕様で、具体的にはF値が変更可能なクリックストップは、
4,5.6,(6.7),8,(9.5),11,(13),16,22 となっている。
例えば、()で示されたF(6.7)などは中間絞り値であるのだが、
何故か、F4とF5.6の間には、中間絞り(F4.5)位置が無い。

200mmレンズにしてはやや長く、不満を感じる事だ。
ただ、この点については、今回使用のシステムでは無理だが、
「ヘリコイド付きアダプター」を使用する回避方法がある。
なお、これも今回使用のX-T1では無理だが、デジタルズーム機能
を搭載している機種であれば、見かけ上の撮影倍率を上げる事は
可能だ。しかし、デジタルズームを使ったとしても最短撮影距離の
長さは変わらないので、寄って写せないから撮影アングルやレベル
(=撮影する為の高さ、例:アイレベル、ウエストレベル)は
制限が大きいままだ。
余談だが、デジタルズーム機能を画質劣化や画素数減少の理由で
嫌う風潮があったり、搭載されていないミラーレス機もあるのだが、
デジタル(スマート系)ズームは、ボケ量やボケ質を維持したまま
構図変更が可能な便利な機能だ。なお、それが「トリミングと等価」
だと思うのであれば、これは実用的には、構図変化による輝度分布の
変化に露出計が追従する(露出補正や輝度レタッチの必要性が低下
する)機種も一部には存在する事と、後処理でのトリミングの
作業負担が減る事、すなわち「編集コストの低減」(ここで言う
コストとは、手間などの労力)の効果が大きい。
特に膨大な数の写真を撮った際などは、いちいちトリミング等を
後からはやっていられないのだ(まあ、ただしデジタルズームを
かけない方がトリミングの自由度は高いので、撮影者がどこまで
編集コストをかけられるのか?という点や、デジタルズームでの
構図を、トリミング後の構図として、ぴったりと決めれるか?
といった撮影者のスキル面にも依存する事であろう)
続く弱点だが、200mm単焦点の小口径(F4)版とは言え、
このレンズの重量は比較的重く、570g近くもある。
これだと今回使用のティルト型アダプターは構造が柔(やわ)
なので、使用する際に、この重さが多少不安だ。

印象があるのか? マニア層においては極めて人気が無い。
あるいは、本レンズよりも後のAF/デジタル時代においては、
200mmという焦点距離は、望遠ズームに内包されてしまい、
単焦点のレンズは初級中級層に対しては「使い難い」という印象を
与えてしまうのか? ともかく、どのユーザー層にも不人気であり
その結果としての中古相場は極めて安価なのだが、それがまた
「安かろう、悪かろう」という印象(誤解)に繋がっていく。
こんな状況なので、およそ、このクラスのレンズをまともに買って
評価した例は少ないだろうし、真の実力値も世に知られる事が無い。
しかしながらMF時代の200mmのF4級では本SMCT200/4は良く写り、
MFのF3.5級でもMINOLTA MC TELE ROKKOR QF 200mm/f3.5
(ミラーレス・マニアックス第68回記事)等も、かなり良く写る、
F2.8級だとAF時代のMINOLTA APO HI-SPEED AF200mm/f2.8
(本シリーズ第4回記事)は素晴らしく良く写るレンズだ。
200mm単焦点という、ありふれたスペックのレンズの中にも、
こうした名レンズが眠っている事が多い。
そういう「掘り出し物/お宝」を発掘する事も、またマニアックな
楽しみ方になるのだと思う。
本SMCT200/4は、もし1000円とか2000円で見かけたら、迷わず
買ってみるのが良い。試写した際、その高い描写力と圧倒的な
コストパフォーマンスに、きっと驚きを隠せない事であろう。
「ならば、高価なレンズって、何の意味があるのだろう?」と
疑問すら感じてしまうかも知れない、それもまた、見聞・見識を
広めるという意味では重要な事だと思う。
---
第3位
評価得点 4.55 (内、コスパ点 5.0)

レンズ購入価格:2,000円(中古)
使用カメラ:OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅡ Limited (μ4/3機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第2回記事で紹介の
1970年代のMF小口径標準レンズ。 ミノルタMC/MD系マウントだ。
当該名玉編記事では、第11位相当にランクインしたが、
コスパ点が満点の5点であった為、本シリーズ記事では、
コスパを重視する採点手法であり、第3位までランクアップした。

小口径標準である。初級層あるいは初級マニアであれば、
「他に、F1.4やF1.2の高級な標準レンズがいくらでもあるのに
何故このレンズなのだ?高いレンズの方が写りが良いだろう?」
という疑問があると思う。
しかしこれがまるっきりの誤解なのだ、私は50mm級標準レンズを
何十本も所有しているが、MF時代~AF時代~デジタル初期の時代
にかけ、F1.2~F1.4級の50mm「大口径」標準レンズと、
F1.7~F2.0級の50mm「小口径」標準レンズが、同一マウントで
併売されていた場合、ほぼ必ずと言っていい程、小口径版の方が
写りが良い。
大口径版は、確かに明るいし、ボケ量も多くとれる、そして必ず
小口径版より高価だ。だから普通はそちらの方が良いレンズだと
思い込み、写りも良いものだ、と信じて疑わない。
まあでも、それは事実では無い。
そして、もし安いレンズの方が、価格の高いレンズよりも性能が
高い、となってしまったら、レンズの商品ラインナップ上も
不自然な事になってしまうかも知れない。

50mm「小口径」標準の方に「性能制限」をかけていた事もある。
具体的な例をあげれば、50mm/f1.4の最短撮影距離は45cmだが、
50mm/f1.8の最短撮影距離を60cmに制限する、などである。
この性能差があれば、近接撮影時において、F1.4版の方が
遥かに被写体深度を浅くする事ができる、つまり「良くボケる」
メーカーあるいは、その営業マンとしては、ユーザー層に対し、
「ほらね、こちらのF1.4版の方が良く背景がボケるでしょう?
だから、こちらのF1.4版の方が値段が高いのですよ」
という理屈を、初級中級層に対して言えるのだ。
(ちなみに、本MC50/1.7も最短撮影距離が50cmと、F1.4級の
45cmに対し、ほんの5cmだけ寄れない仕様となっている)
だけど、こういう風に、メーカーの都合で、低価格商品に対して
差別化する事は、個人的には「好ましく無い」と思っている。
最短撮影距離の件ではなく、カメラにおいても性能を出し惜しみ
する例は、その後のAF/デジタル時代での普及版(低価格)一眼レフ
においても、非常に良くあった(例:普及機は連写速度が遅い等)
のだが、まあ、あえてそういった機種は買わないようにしていた。
性能・スペックに関する資料を良く読み込めば、そうした「仕掛け」
があるだろう事が想像できるからだ。
メーカー側の「売りたい」という気持ちと、ユーザー側の「買いたい」
という心理をバランスさせるのは、一種の「勝負である」と
私は思っている。つまり、値段と本来の絶対的価値が見合わない物
(=コスパの悪い物)を買わされてしまったら「ユーザー側の負け」
だと私は思っている訳だ。

に中古市場で流れていた、一種の「処分品」である、だから、
これの値段(2,000円)と、実際の価値は釣り合わない。
「釣り合わない」というのは良い意味の方であり、すなわち
コスパが極めて良い「お買い得品」であったと言う事だ。
「他にもMF50mm小口径はいくらでもあるだろう?何故この
レンズが選ばれているのか?」というマニア層の疑問に関してだが、
まず、確かにMF50mm小口径は色々あって、たいていそのどれも
が良く写り、しかも、それらの多くは安価な中古相場だ。
ついでに言えば、その殆どの小口径標準は、同じようなレンズ構成
で設計されていて、性能上の差も、あまり(ほぼ全く)出ない。
しかし、それでもたとえば、ニコン版のAi50mm/F1.8Sとか、
コンタックスのP50mm/F1.7とかは、中古相場が高価すぎるのだ。
(ブランド力が高い為、相場も高額になると言う理由だ)
それから、マウントの問題もある。
MF時代のマウントと現代のデジタル一眼レフのマウントにおいて
かろうじて形状互換性があるのは、NIKON FとPENTAX Kである。
(まあ、実際には形状が同じでも様々な使用制限は出てくる)
ミノルタMC/MDやキヤノンFDに関しては現代の一眼レフでの
使用は難しい、なので中古相場が安価になっていたのは当然だが
現代においては、ミラーレス機を用いることで、そうしたMDや
FDのレンズを何ら制限なく使う事ができるようになった。

安価である事は確かであり、まあ、それらの状況から、本レンズは
安価に購入でき、結果的に他社レンズよりもコスパが良い訳だ。
---
第2位
評価得点 4.55 (内、コスパ点 5.0)

レンズ購入価格:12,000円(中古)
使用カメラ:SONY α65(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第2回、ハイコスパ第10回記事
で紹介の、2010年代のAF単焦点準広角(標準画角)レンズ。
α(A)マウントであり、APS-C機専用の為、換算画角は
約52mm相当となる。
いわゆる「エントリーレンズ」である。
本シリーズ記事開始当初は「ランクインするのは、マクロレンズと
エントリーレンズばかりになってしまうのでは?」と危惧したが
ラストのBEST4に入ったエントリーレンズは、幸か不幸か本レンズ
のみである。

(高スペック)である事だ。
具体的には、まず、AFの35mm/F1.8(級)という仕様のレンズ
の中では本レンズが最も安価な事だ。
一般的には、一眼レフ用のAFレンズで35mmの単焦点では、
F1.4級の物はかなり高価であり、開放F値がそれより半絞り暗い
F1.8級の物も(特にフルサイズ用は)高価となる。
例えばタムロンのSP35mm/F1.8(F012)(レンズマニアックス
第13回記事等で紹介)の定価は9万円もする。
「このレンズは最新の高画質仕様だから高い」と言うならば・・
キヤノンのEF35mm/F2 IS USM(未所有)の定価が83,000円だ。
(注:旧型のEF35mm/F2は、ミラーレス第68回記事で紹介、
そのレンズは1990年の発売で定価38,300円であった)
「これもフルサイズ対応の高性能レンズだ」と言うならば・・
エントリーレンズのカテゴリーに属すると思われる、ニコンの
AF-S DX NIKKOR 35mm/F1.8G(APS-C専用、ハイコスパ
第26回記事)の定価が35,000円である。
対して、本DT35mm/F1.8(SAL35F18)は定価24,000円と
格段に安価である。(注:ここにあげた定価はいずれも税別)
なお、MFレンズであれば、中一光学のCreator 35mm/F2
(本シリーズ第4回記事)は、実売定価が約2万円と、さらに安価で
あるが、これは中国製のローコストレンズ(ただし品質や描写力は
悪くない)であるから、まあ例外的だ。
それから、「重要な仕様」は焦点距離と開放F値だけでは無い、
最短撮影距離だが、本DT35/1.8では驚異の23cmである。
近年に発売されたTAMRON SP35/1.8が最短20cmで、本レンズを
上回るまで、長らく本DT35/1.8が最も寄れる35mm単焦点であった。
(注:35mmマクロレンズや、オールド海外製レンズを除く)
あと、重量であるが、本DT35/1.8は170gと軽量だ。
比較をするのは少々可哀想だが、高性能レンズTAMRON
SP35/1.8(F012)は480g以上と3倍近くも重い。
なお、本レンズが軽量である事と引き換えに、作りがチャチ
(プラスチッキーで、安っぽい)と言う弱点を持つ。

値段を越えた仕様・性能を持つレンズという事であり、これが
すなわち「代表的なハイコスパレンズである」と言えよう。
なお、私の中古購入価格12,000円は、少し前の相場であり
やや高目だ、2019年現在では1万円以下の価格で購入可能
だと思う。
この値段でこの性能(仕様)であれば、ほとんど文句は無いとは
思うが、一応弱点をあげておくと、まず前述の作りの悪さ
(高級感が無く、安っぽい)と、描写力があまりスペシャルという
訳でもなく、まあ普通の写りのレンズである事だ。
寄れる(最短撮影距離が短い)のは良い事だが、被写界深度が浅い
写真を撮る際には、ボケ質の破綻にも若干注意しなければならない、
常にボケ質が良い写真が撮れると言う事でも無いのだ。
まあでも、「エントリーレンズ」という物は、基本的にどれを
選んでも後悔は無いであろう、なにせ、メーカーとしては、
それを「交換レンズのお試し版」として販売し、初級ユーザーが
それを気に入ってもらって、自社のより高価な、レンズやカメラ
本体の販売促進を目的としている訳だからだ。
もしエントリーレンズが不満足な性能だったら、それを買った
ユーザーは二度とそのメーカーの製品を買ってくれなくなる、
という、市場戦略上、極めて重要なポジションのレンズだ。
よって、価格を越えた性能がある事は言うまでも無い、すなわち
エントリーレンズは、どれも極めてコスパが良い訳だ。
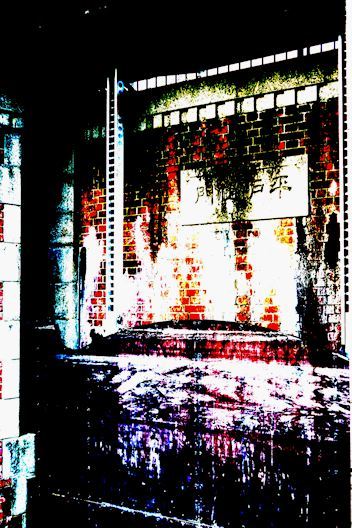
持たない、「どうせお金を出すのであれば、最高性能のものが
欲しい」という考え方であろう。まあ確かに、本レンズには
超音波モーターは入っていないし、超高画素時代に対応した
最新の高解像力設計という訳でもない、そしてフルサイズ対応
でも無い。しかし、それらの「付加価値」が、そのユーザー層に
本当に必要なのかどうかは状況によりけりだ。
不要なまでのスペックのものを高価に購入する事は、結局は
「メーカーの利益」として還元されてしまう(=ユーザーの負け)
という事だ。
が、このあたりの判断はユーザーの志向や機材購入コンセプトに
よりけりだ、「無駄にお金を払いたくは無い」のか、あるいは
「お金をかけても最高のものが欲しい」と思うかは、ユーザー
個人の価値観にもゆだねられるであろう。
ただ、その「価値観」は極めて重要だ。良いモノと、そうで無い
モノを見分ける、あるいは自分にとって何が必要で、何が必要
では無いのかを見分ける力が無ければ、ユーザーの機材購入
コンセプトなんて、あって無いような事となってしまう。
事実、本レンズDT35/1.8は、最短撮影距離といった性能面を
とってみれば、全35mmレンズ中トップクラス(長らく1位)
であったのだ、同マウントでの高価な上位製品AF35mm/f1.4
(ミラーレス第60回記事)を、「何かを」期待して購入して
「思ったほど寄れない(最短30cm)」などと不満を言って
いたら、何をしているのかわからなくなってしまうであろう・・
まあ、そういう事が「価値観」に繋がるのだと思う。
---
さて、いよいよラストは栄光の第1位だ。
評価得点 4.75 (内、コスパ点 5.0)

レンズ購入価格:15,000円(中古)
使用カメラ:SONY α77Ⅱ(APS-C機)
ミラーレス・マニアックス名玉編第4回記事で紹介の
1980年代後半のAF標準等倍マクロレンズ。
ミノルタα→SONY α(A)マウント、銀塩時代のレンズであるがら
勿論フルサイズ対応だ。

SONY製50mm/F2.8Macro (SAL50M28)に繋がるが、約30年間
に渡り光学系に大きな変更は無いと思う。つまり「最初期型から
極めて完成度が高かった」と言う事であり、同じマクロレンズ
として完成度の高いロングセラー名玉TAMRON SP90mm/f2.8
(1996年の72E型より続く。本シリーズ第10回記事参照)
と肩を並べる歴史的名マクロレンズだと思う。
最初期型である本レンズの発売年度は不明だが、恐らくは
1980年代の後半、ミノルタα-7000(1985年、未所有)と
同時代だと思われる。このα-7000はAF一眼レフとしては
初の実用的カメラであり、市場全般に大きなインパクトを
与え、「αショック」と呼ばれた。
これ以降の各社のカメラ・レンズは一斉にAF化に追従、
1980年代後半では「AFにあらずんば、カメラにあらず」と
いう雰囲気が市場には漂っていた事であろう。
この「AF至上主義」は、交換レンズにもおよび、MFを軽視
あるいは無視した仕様のものもあった。
だいたい型番からして、α用の交換レンズは「AF何々」
という名称である。

極めて狭い。
つまり「AFがあるのだから、MFでは撮らないでしょう?」という
仕様になっていると言う訳だ、だが勿論、全ての撮影シーンで
AFが有効に機能する事は無い。マクロ撮影ならば、なおさらで
当時のAFの精度不足、測距点が少なく構図の自由度が無い、
等の問題により、「MFはやはり必要」という風潮になっていく。
その後の改良品(New型、D型、SONY型)では、バージョン
アップのたびに、MF時の操作性向上の為にピントリングの幅が
広くなっていく。
ばお、中古相場はバージョンが新しくなる程、当然高価になる、
最初期型の場合は、現代での相場は1万円以下であり、
性能からすると極めて安価で、コスパが最高レベルに高い。
(それ故に、本レンズもコスパ点は満点であり、描写力などの
性能を加味して、栄光の第1位となった次第だ)

使用している状態では実用的な面で大きな不満は無い筈だ。
まあ重箱の隅をつつくように言えば、解像力が低いとか
逆光耐性、ボケ質破綻、AF精度、などが上げられるが、
いずれも軽微なレベルであるし、30年以上も前のレンズと
思えば、やむを得ない節もある。
それに、もしこれらが重欠点であるならば、長い年月の間に
製品は改良されていく筈だ、その改良点が、少なくとも光学系
においては、ほとんど無かった、という状況が、すなわち
問題点には至らない、という事実を示している。
なお、こういうケースを鑑みて、私の場合は、一般的な交換
レンズ製品において、前モデルと後継モデルでの間で光学系の
変更が無かった際、その前モデルを「十分に描写力が高かった」
と判断して、優先的に購入する事としている。
新モデル発売により、前モデルの中古価格は大きく下落するのが
常であるので、極めてコスパの良い買い物が出来る訳だ。

ここまで色々なハイコスパレンズを紹介してきたのだが
「いくら安価にレンズを買っても、結局沢山買っていたら
コストがかかってしょうが無いじゃあないか?」という
疑問もあるだろう。
だが、私としては、「できるだけ沢山のレンズを知りたい」
という「探究心」もまた、1つの機材購入コンセプトとして
ある訳だ。まあ、なにかの方向性をもって突き詰める事が
「趣味」、あるいは「マニア道」としては、切っても切れない
重要な要素となる。
本記事の読者層としては、単純に「安くて良いレンズが知りたい」
というニーズがあるのならば、記事を読んで気に入ったレンズ
を探して買えば良い訳だ。そういうシンプルな話である。
注意点だが、機材の購入コンセプトが人それぞれであるならば
高コスパレンズを買ったところで満足できない人も居る、と言う
点だ。例えば、「いくら性能は良くても、こんな安っぽい作り
のレンズは嫌だ」という考え方を持っている人も居るであろう。
まあでも、人の「価値観」は変化する場合もある。
いままで「安かろう、悪かろう」と食わず嫌いをしていたのが
試しに買ってみたら、ハマってしまうというケースも有り得る。
でもまあ、それは悪い話では無い、価値観は変化しても構わない
訳だ。
結局、重要なのは、別にそれが変わっていっても良いのだが、
いかに自分自身の強い「価値観」を持つか、という点だと思う、
さもないと、「誰かが良いと言ったから買う」などと、
他人まかせの機材購入コンセプトしか持てなくなってしまうで
あろう、それは、一番やってはいけない事だと思っている。
以上で本シリーズ記事を終了する。